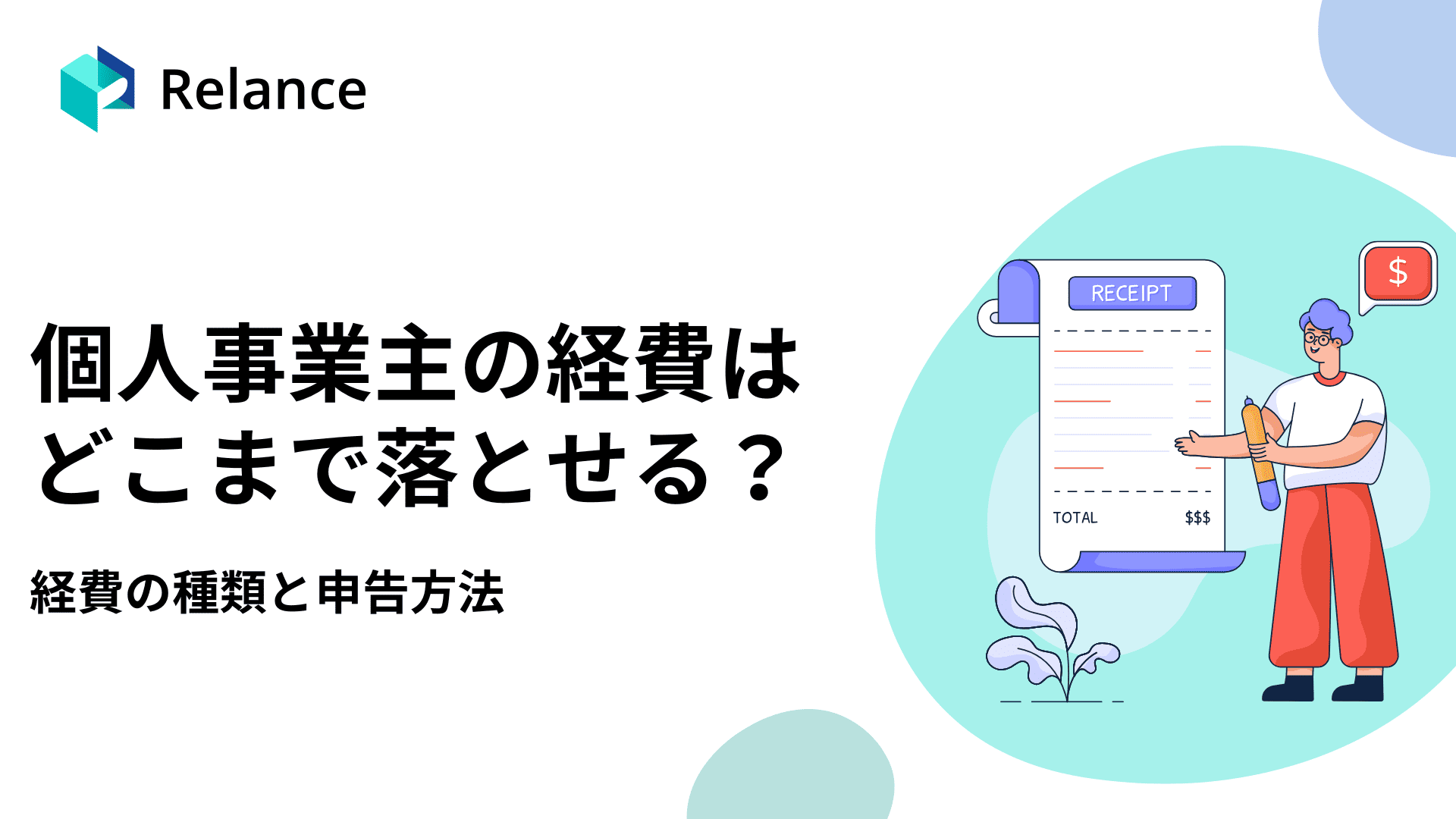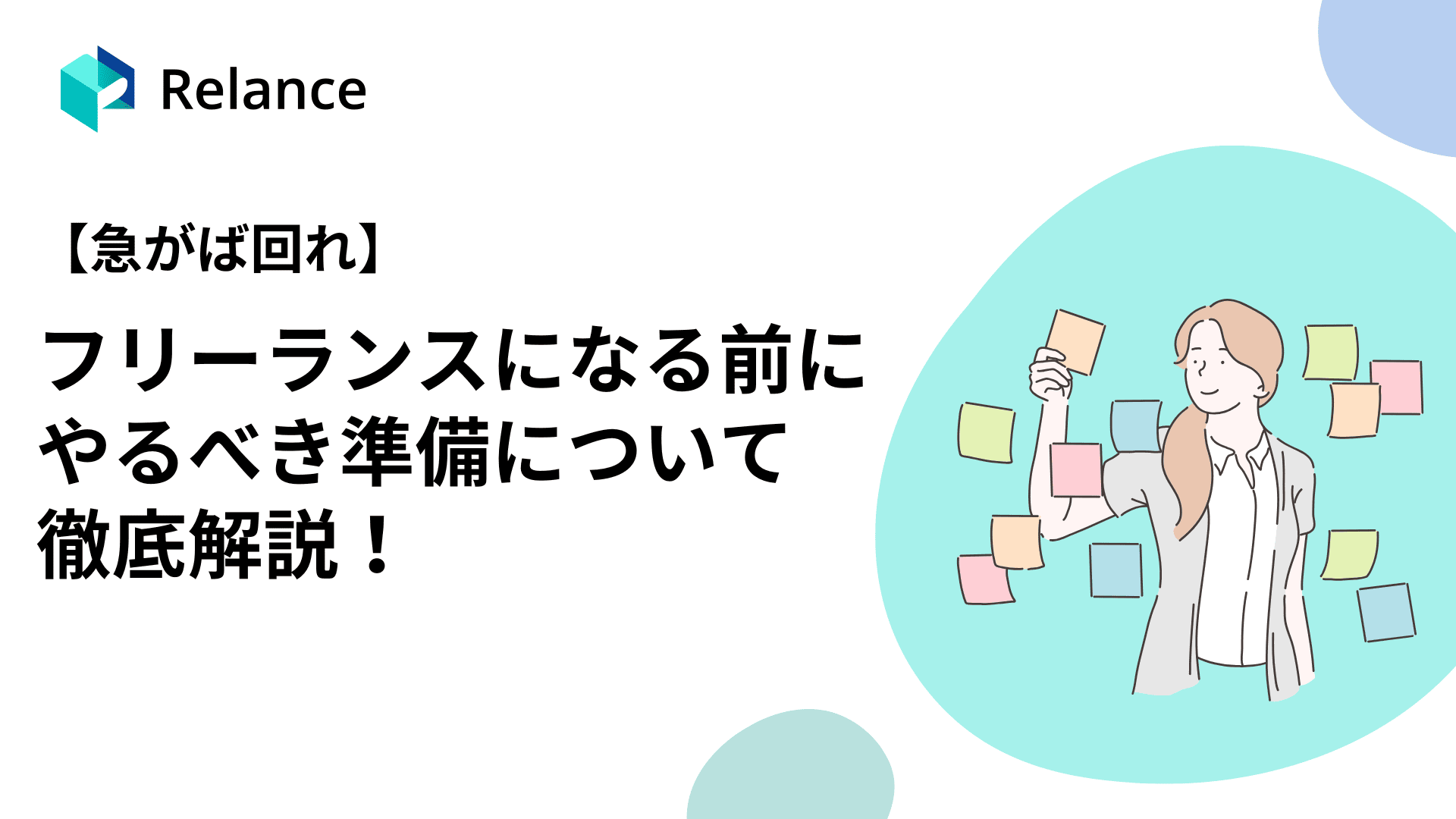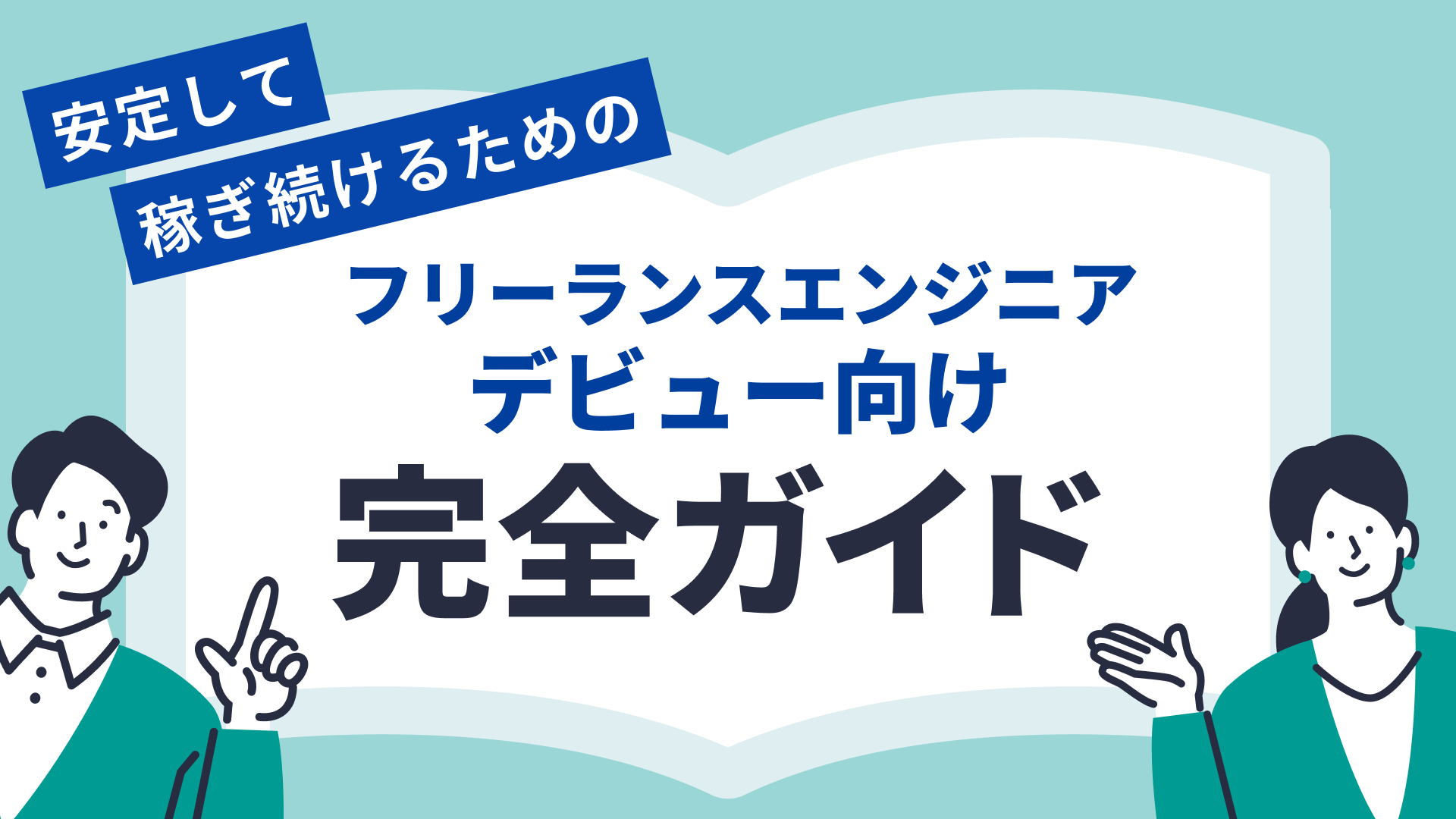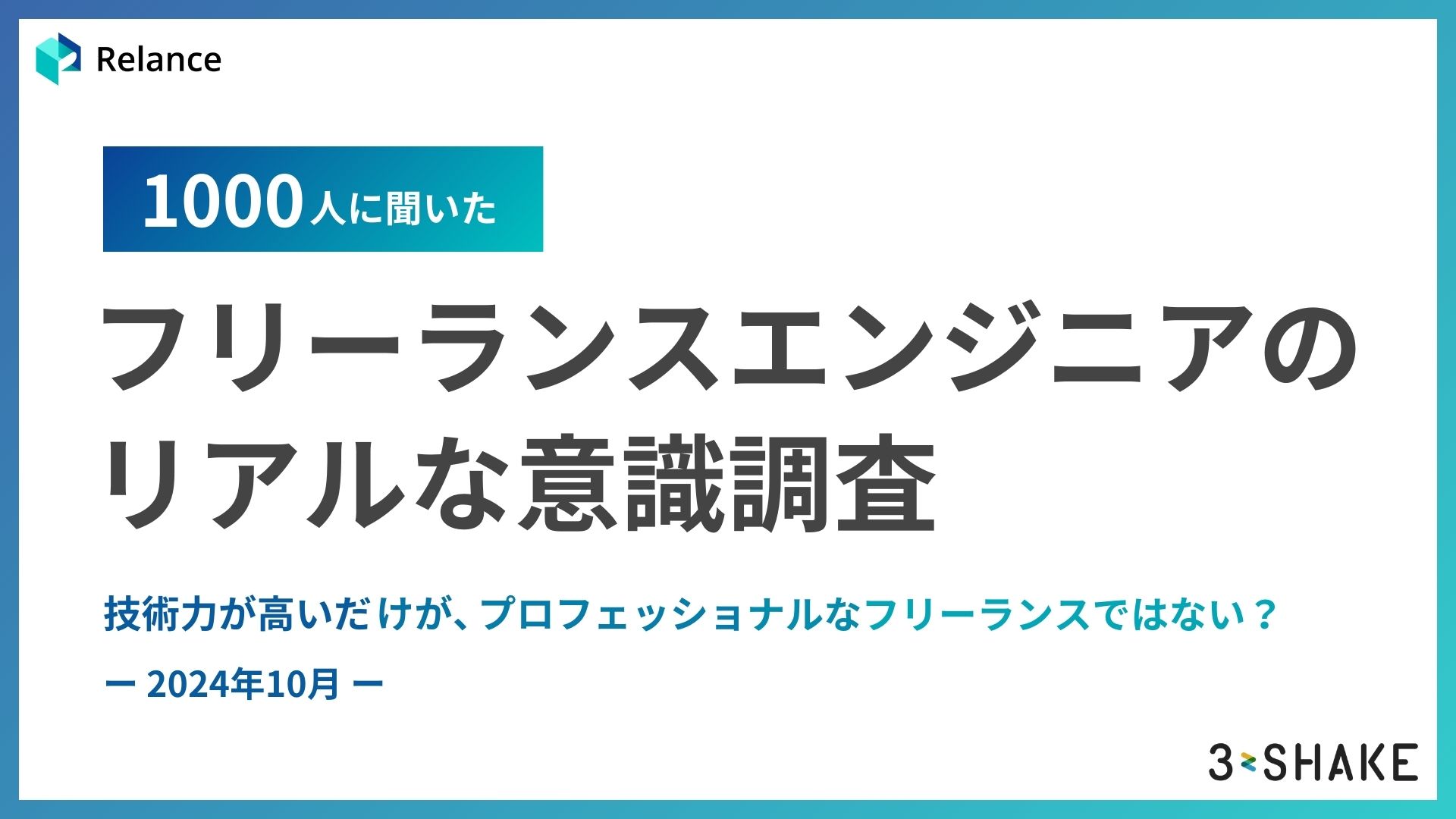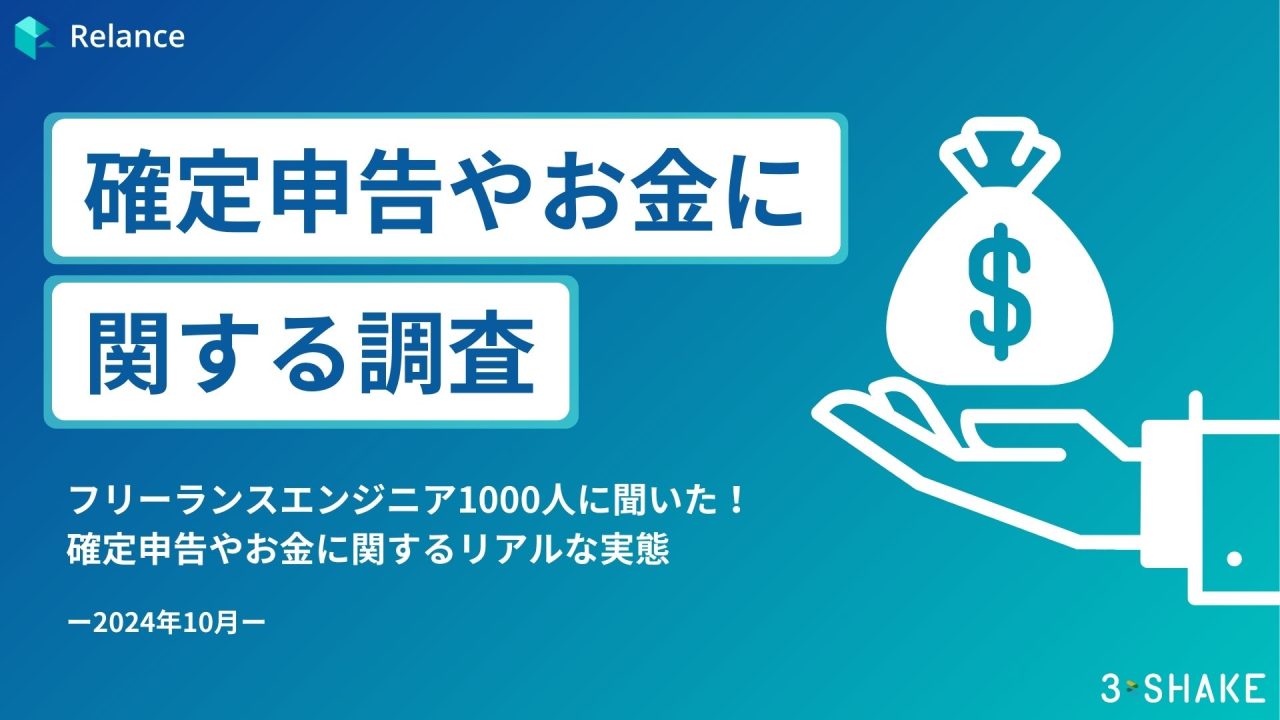フリーランスの保険完全ガイド|保険の種類や保険料の計算方法を解説!
企業などに属さず働くフリーランスの場合、加入する健康保険や年金などが会社員とは異なります。
会社員よりも不安定な働き方である分、体調を崩した場合や将来の生活に対して、しっかりと備えたいと考える方も多いことでしょう。
原則として自身で保険料のすべてを支払わなければならないフリーランスとしては、健康保険料がどれ程かかるのかも気になるところです。
本記事では、フリーランスが加入できる健康保険や民間保険、そして公的機関運営の制度について解説します。保険料の計算方法についてもご紹介しているので、ぜひご一読ください。
Relanceは、エンジニア目線でスキルや経験にマッチした高単価案件をご紹介しております。
メルマガで案件の最新情報を配信しているので、ぜひ登録してください!
⇒Relanceの案件速報を受け取る【無料】
目次
フリーランスが加入できる健康保険
国民皆保険制度のある日本では、原則として国民全員が公的医療保険に加入し、安い医療費にて高度な医療を受けられるようになっています。もちろん、フリーランスも同様です。
ただし、フリーランスの健康保険は、会社員と全く同じというわけではありません。
フリーランスが加入できる健康保険としては、主に以下4つのパターンが挙げられます。
- 国民健康保険に加入する
- 会社員時代の健康保険を任意継続する
- 家族の健康保険組合に扶養で入る
- フリーランスが加入できる健康保険組合もある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.国民健康保険に加入する
フリーランスは、市区町村運営の公的な地域保険である「国民健康保険」に加入することが原則です。
国民健康保険への加入手続きは、お住まいの市区町村役場にて、会社を退職してから14日以内におこないます。
会社員が加入する健康保険の場合は、職場と加入者(従業員)とで保険料を折半するのが一般的です。その点、フリーランスが加入する国民健康保険の場合は、加入者が全額を負担することとなります。
また国民健康保険には、会社員の健康保険にあるような傷病手当金や出産手当金などもありません。
国民健康保険料や必要となる書類などについては、市区町村によって異なります。
国民健康保険加入時に必要となるものは、以下を参考にしてください。
- 職場の健康保険資格喪失証明書や扶養削除証明書
- 身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードやマイナンバー通知カードなど)
- 保険料口座振替用のキャッシュカードまたは通帳
- 印鑑 など
国民健康保険には、フリーランス(個人事業主)本人だけでなく、その家族も加入できます。ただし、被扶養者となるのではなく、それぞれに保険料が課される点には留意が必要です。
国民健康保険への加入時には、同時に国民年金の加入手続きもおこなっておきましょう。
2.会社員時代の健康保険を任意継続する
会社を退職しフリーランスへと転向する場合は、健康保険の被保険者資格を喪失しても、会社員時代の健康保険を任意継続できます。
ただし、全国健康保険協会 協会けんぽの場合を例に挙げると、以下2つの条件を満たさなければなりません。
- 健康保険の被保険者期間が、資格喪失日の前日までに継続して2か月以上あること
- 資格喪失日(退職日の翌日など)から20日(20日目が土日祝日の場合は翌営業日)以内に任意継続被保険者資格取得申出書を提出すること
「任意継続被保険者資格取得申出書」を記入した上で、退職日の翌日から20日以内に、お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部に提出します。
会社を退職後の最長2年間、健康保険の任意継続が可能です。
保険料は当然、会社との折半ではなくなり、全額が自己負担となる点には注意してください。
任意継続の場合、保険料は原則として2年間変わりません。ただし、以下のケースを除きます。
- 任意継続中に40歳となり介護保険第2号被保険者に該当した場合
- 任意継続中に65歳となり介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合
- 都道府県別の健康保険料率・介護保険料率が変更された場合
- 標準報酬月額の上限が変更となった場合
- 保険料率の異なる都道府県へと転出した場合
なお、健康保険の任意継続は、保険料の支払いを1日でも延滞すれば即脱退となってしまうため、注意しましょう。
参考:健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について|全国健康保険協会 協会けんぽ
参考:任意継続の加入条件について|全国健康保険協会 協会けんぽ
参考:任意継続の加入手続きについて|全国健康保険協会 協会けんぽ
3.家族の健康保険組合に扶養で入る
個人事業主、フリーランスという立場であっても、一定の条件を満たせば、家族が加入している健康保険組合に被扶養者として加入することも可能です。
その場合、国民健康保険よりも保険料が安くなる可能性があります。
条件は、各健康保険組合によって異なります。
基本的に2024年9月現在は、年間の収入が130万円を超える場合には家族の扶養から外れるため、先にご紹介した国民健康保険に加入しなければなりません。
そのほかの条件に関しても、家族が加入している健康保険組合が掲げている条件を事前にしっかりと確認しておきましょう。
参考:「年収の壁」対策がスタート!パートやアルバイトはどうなる?|政府広報オンライン
4.フリーランスが加入できる国民健康保険組合もある
フリーランスが加入できる「国民健康保険組合」もあります。
国民健康保険組合とは、特定の職業に就いている者が加入できる保険制度です。
場合によっては、国民健康保険よりも保険料が安くなることもあるでしょう。
フリーランスが加入できる代表的な国民健康保険組合は、以下を参考にしてください。
- 文芸美術国民健康保険組合…日本国内に住む、文芸・美術・著作などの芸術活動をおこなっている組合加盟団体会員、またその家族が加入できる国民健康保険組合です。保険料は収入にかかわらず一定ですが、組合加盟団体の会員費は別途支払う可能性があります。
【2024年度保険料】
| 組合員 | 1人あたり月額25,700円(医療分19,900円、後期高齢者支援金分5,800円) |
| 家族 | 1人あたり月額15,400円(医療分9,600円、後期高齢者支援金分5,800円) |
| 介護保険料(満40歳から64歳までの被保険者(組合に加入するすべての者)) | 1人あたり月額5,700円 |
月額の保険料=組合員+(家族×該当人数)+(介護保険料×該当人数)
- 東京美容国民健康保険組合…美容業界で働く者を対象とした健康保険組合です。東京都内に事業所がある者とその家族に限って加入できます。
【2024年度保険料】
| 一般被保険者(40歳~64歳以外)<医療給付費分+後期高齢者支援金分(3,500円含む)> | 介護納付金賦課被保険者(40歳~64歳)<医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分(3,000円)> | |
| 事業主組合員1人あたり | 月額 20,000円(均等制) | 月額 23,000円(均等制) |
| 従業員組合員1人あたり | 月額 14,500円(均等制) | 月額 17,500円(均等制) |
| 同一世帯家族1人あたり | 月額 9,500円(人頭割~組合員・世帯主負担) | 月額 12,500円(人頭割~組合員・世帯主負担) |
| 同一世帯家族(未就学児)1人あたり※義務教育就学前 | 月額 6,000円(人頭割~組合員・世帯主負担) | 該当なし |
- 関東信越税理士国民健康保険組合…関東信越税理士会会員(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県の6県を区域とする)の税理士とその職員、家族が加入できる健康保険組合です。
【2024年度保険料】
| 6歳未満 | 6~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | |
| 税理士勤務税理士 | 基礎賦課分(医療分)26,000円+後期高齢者支援金分5,200円=31,200円 | 基礎賦課分(医療分)26,000円+後期高齢者支援金分5,200円+介護納付金分6,200円=37,400円 | 基礎賦課分(医療分)26,000円+後期高齢者支援金分5,200円=31,200円 | |
| 職員 | 基礎賦課分(医療分)15,000円+後期高齢者支援金分5,200円=20,200円 | 基礎賦課分(医療分)15,000円+後期高齢者支援金分5,200円+介護納付金分6,200円=26,400円 | 基礎賦課分(医療分)15,000円+後期高齢者支援金分5,200円=20,200円 | |
| 家族 | 基礎賦課分(医療分)8,000円 | 基礎賦課分(医療分)8,000円+後期高齢者支援金分5,200円=13,200円 | 基礎賦課分(医療分)8,000円+後期高齢者支援金分5,200円+介護納付金分6,200円=19,400円 | 基礎賦課分(医療分)8,000円+後期高齢者支援金分5,200円=13,200円 |
これらの職業、地域に属している場合は、ご紹介した特定の国民健康組合に加入するのもおすすめです。
参考:文芸美術国民健康保険組合
参考:東京美容国民健康保険組合
参考:関東信越税理士国民健康保険組合
フリーランスの国民健康保険料の計算方法
フリーランスは、会社員とは違い、国民健康保険料のすべてを自身が支払うと先述しました。では、実際にどの程度の保険料を支払うのでしょうか。
まず、前提として、国民健康保険料の計算方法は市区町村ごとに異なります。そのため、お住まいの地域の国民健康保険料、計算方法を確認してください。
ここでは、1つの例として、東京都世田谷区の国民健康保険料と計算方法をご紹介します。
- 国民健康保険料=基礎(医療)分保険料+後期高齢者支援金分保険料+介護分保険料
基本は、上記の計算式で求められます。
基礎(医療)分は、国保財政の基礎財源となるもので、最高限度額は65万円です。計算方法は以下をご覧ください。
- 基礎(医療)分年間保険料=(所得割額:加入者全員の賦課基準額×8.69%+均等割額:加入者数×49,100円)×加入月数/12か月
※賦課基準額は、前年の所得額より住民税基礎控除430,000円を差し引いた金額。
後期高齢者支援金分の最高限度額は24万円であり、計算方法は以下のとおりです。
- 後期高齢者支援金分年間保険料=(所得割額:加入者全員の賦課基準額×2.80%+均等割額:加入者数×16,500円)×加入月数/12か月
介護分は、40歳~64歳の加入者が支払う保険料であり、最高限度額は17万円です。計算方法は以下のようになります。
- 介護分年間保険料=(所得割額:40~64歳の加入者の賦課基準額×2.36%+均等割額:加入者数×16,200円)×加入月数/12か月
世田谷区の令和6年度国民健康保険料早見表をもとに、38歳、給与所得4,000,000円、4月に国民健康保険に加入したフリーランスの場合を例にとって、計算してみましょう。
- 給与所得 4,000,000円-住民税基礎控除 430,000円=令和6年度国民健康保険料賦課基準額 3,570,000円
- 基礎(医療)分=3,570,000円×8.69%+49,100円=359,333円
- 後期高齢者支援金分=3,570,000円×2.80%+16,500円=116,460円
【年間保険料=基礎(医療)分 359,333円+後期高齢者支援金分 116,460円=475,793円】
ただし、上記はあくまで経費や青色申告の税制優遇などを考慮しない場合の保険料です。経費など状況によって国民健康保険料も変わる点にはご注意ください。
フリーランスは民間保険に加入するべき!
フリーランスは、すべてにおいて自身に責任の所在があり、自身で対応していかなければならない働き方です。
企業に所属している会社員ならば、何かあった際にも、会社に保障・補償してもらえたり、給付金を得られたりもするでしょう。しかし、フリーランスはそうではありません。
前述したように、傷病手当金・出産手当金といったものもないため、病気やケガ、あるいは出産・育児などで働けなくなったときには、収入そのものが途絶え、生活にも大きく影響します。
また、フリーランスの場合は厚生年金もないため、老後の蓄えについても大きな不安が伴います。
このように、何かと不安定なフリーランスだからこそ、万が一に備えて民間保険に加入することが望ましいといえるでしょう。
フリーランスが加入できる民間保険の例
フリーランスとして働いていく以上、万が一に備え、民間保険に加入することが望ましいと前述しました。
では、フリーランスが加入できる民間保険には、どのようなものがあるのでしょうか。
主な例としては、以下のような民間保険が挙げられます。
- 所得補償保険・就業不能保険
- 医療保険
- 個人年金保険
- 終身保険
- 賠償責任保険
1つずつ内容を確認していきましょう。
1.所得補償保険・就業不能保険
病気やケガなどで働けなくなった場合に備えて、所得補償保険や就業不能保険への加入をおすすめします。
所得補償保険は、その名のとおり、病気・ケガなどで一時的に働けなくなった場合の収入を補償してくれる保険です。
また、就業不能保険は、病気・ケガなどで長期的に働けなくなった場合の収入を補償してくれます。
会社員の健康保険で補償されている傷病手当金(最大1年6か月間、給与の約3分の2を受取り可能)に代わるものであるため、フリーランスなら必須で加入しておきたい保険といえるでしょう。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会 協会けんぽ
2.医療保険
フリーランスでも加入できる民間の医療保険は、公的医療保険ではカバーしきれない費用などを給付してくれる保険制度です。
国民健康保険では、医療費の自己負担を3割程度に抑えることはできるものの、原則として、先進医療技術料、個室や少人数の病室に入院した際の差額ベッド代、入院中の食事代などは対象外となってしまいます。
その点、民間の医療保険では、入院・手術などの際に給付金を受け取れるため、上記のようなリスクに備えられます。
3.個人年金保険
個人年金保険とは、公的年金とは別に、老後の生活資金を補う私的年金です。
会社員に補償されている厚生年金がないフリーランスは、公的年金だけでは老後の生活費を十分に賄えるといえません。
老後の生活を保障するために、個人年金保険への加入も検討したいものです。
個人年金保険は、受取期間や運用方法を選択できます。
受取期間によって主に「確定年金」「有期年金」「終身年金」の3種に分かれ、運用方法も「定額個人年金保険」「変額個人年金保険」の2種類があります。
個人年金保険は、所得控除の対象であるため、税制優遇の面でもメリットが大きいといえるでしょう。
ただし、払込期間の途中で解約してしまうと元本割れの可能性もあるため、注意が必要です。
また、契約時に年金受給額が決定するため、インフレが進むと資産価値が目減りしてしまうデメリットもあります。
とはいえ、長く、計画的に運用できる方なら、加入しておいて決して損はない保険です。
参考:個人年金保険のメリット・デメリットを紹介!種類や公的年金との違いも解説|明治安田生命
4.終身保険
終身保険は、被保険者が死亡、または保険会社所定の高度障害状態となった場合に支払われる保険金です。その名のとおり、保障が一生涯続きます。
主な目的は、一家の稼ぎ主に万が一の事態があった際に、家族及び遺族の経済的負担を軽減させることです。
終身保険は、さまざまな保険会社から多様な保険商品が販売されています。資料を取り寄せるなどして、保障内容や費用などを十分に比較検討しましょう。
自身のためというよりも、家族のために考慮すべき保険といえます。
5.賠償責任保険
フリーランスとして是が非でも加入しておきたいのが、賠償責任保険です。
賠償責任保険は、情報セキュリティリスクや知財に関するトラブル、財物の破損、ビジネスにおける事故などの損害賠償金や、弁護士費用を補償してくれます。
フリーランスは、企業と比較すると賠償資金力が乏しく、そのあたりを懸念するクライアントも少なくないでしょう。賠償責任の面で、案件獲得に影響することもあるかもしれません。
賠償責任保険に加入することで、フリーランス特有のリスクに備えましょう。
フリーランスの賠償責任補償としては、プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会への登録もおすすめです。
プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会の一般会員として登録すると、損害賠償責任補償が自動で付帯されます。さまざまなフリーランス向けサービス(福利厚生サービス)を、割引価格で利用できるのも魅力的です。
年会費として1万円がかかりますが、その費用は経費として計上することもできます。
会員データベースにプロフィールを公開すれば、案件獲得の足掛かりとなることも期待できるでしょう。
参考:フリーランスの保険|プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会
フリーランスでも加入できる公的機関運営の制度
フリーランスが加入できる民間保険についていくつかご紹介しましたが、実は、公的機関運営の制度にも、個人事業主・フリーランスが加入できるものがあります。
- 小規模企業共済制度
- 中小企業退職金共済制度
- 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
上記3つの共済制度について詳細を解説しますので、内容を確認し、将来に備えましょう。
1.小規模企業共済制度
小規模企業共済制度は、個人事業主や、小規模企業の経営者・役員のための積立退職金制度です。
掛金は、全額が所得控除対象となります。
月々の掛金に関しては1,000円〜70,000円まで500円単位で自由に設定でき、加入後も掛金の増額・減額が可能です。
退職時・廃業時に共済金の受取りができ、受取方法は「一括」「分割」「一括と分割の併用」から選択できます。
低金利の貸付制度が利用できることもメリットです。
退職金制度のないフリーランスにとって、老後に備えられる制度といえるでしょう。
2.中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済制度は、中小企業の従業員を対象とした、国の退職金制度です。
従業員を雇用している個人事業主が加入できます。
毎月、事業主が掛金を支払い、従業員が退職した際には中小企業退職金共済事業本部から直接退職金が支払われます。
掛金は、損額または必要経費として全額非課税です。
また、掛金に関しては、国からの助成制度も設けられています。
ただし、従業員の加入同意が必要、小規模企業共済制度に加入していない、など一定の条件があるため、注意が必要です。
参考:中小企業退職金共済制度|独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
3.経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先が倒産した場合などに、無利子で必要資金を借りられる制度です。
保証人も必要ありません。
経営セーフティ共済に毎月一定の掛金を支払うことで、取引先の倒産によって資金繰りが悪化したり、売掛金の回収ができない、といった場合に備えられます。
掛金は月に5,000円~20万円までの範囲内(5,000円刻み)で自由に設定可能です。
加入条件は業種によって異なるため、別途確認してください。
借入額の上限は、以下の内いずれか少ないほうの額となります。
- 回収困難となった売掛金債権等の額
- 拠出した掛金額の10倍(最高8,000万円)
ただし、あくまで借入であるため、いずれは返済しなければなりません。
事業における経理の内容が不透明であったり、所得税・法人税などを滞納している場合などには、信用度の低さから加入できないこととなっています。
2024年11月からはフリーランスも労災保険の特別加入対象
2024年9月現在、フリーランスは、原則として労災保険に加入できません。
しかし、2024年11月より、フリーランス(特定受託業務に従事する者)も、労災保険の特別加入対象となることが決定しました。
労災保険は、労働者が仕事や通勤において被った災害に対し補償する制度ですが、
労働者以外の者でも、一定の条件を満たす場合に任意加入、補償を受けられます(特別加入)。
2024年11月からは、特定フリーランス事業も労災保険の特別加入対象となるため、仕事中・通勤中のケガ・病気・障害、また死亡などについて、補償を受けられるようになります。
具体的な補償は、ケガ・病気の治療に必要な給付、ケガ・病気などによって休業する間の給付、死亡した際の遺族への給付などが支給される、といった内容です。
特定の事業・作業ごとに、それら特別加入団体を通じて、労災保険の特別加入ができます。
詳しくは、厚生労働省のサイトを参照してください。
参考:令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります|厚生労働省
まとめ
本記事では、フリーランスが加入できる健康保険、民間保険、公的機関運営の制度について解説しました。
会社員と比較し保障や補償が少なく、不安定な面の多いフリーランスですが、国民健康保険に加えて民間保険や公的機関運営制度に適宜加入することで、さまざまなリスクに備えられるようになります。
2024年11月からは、労災保険への特別加入も認められます。
フリーランスを取り巻く環境は年々変化してきており、今後新たな保険・制度に加入できる可能性にも十分に期待できるでしょう。
先が見えにくい、足場が不安定な働き方であるからこそ、自身を守るために制度について学び、リスクに備えるようにしてください。
本記事がその一助となれば幸いです。
無料で高単価案件を紹介してもらう
関連記事