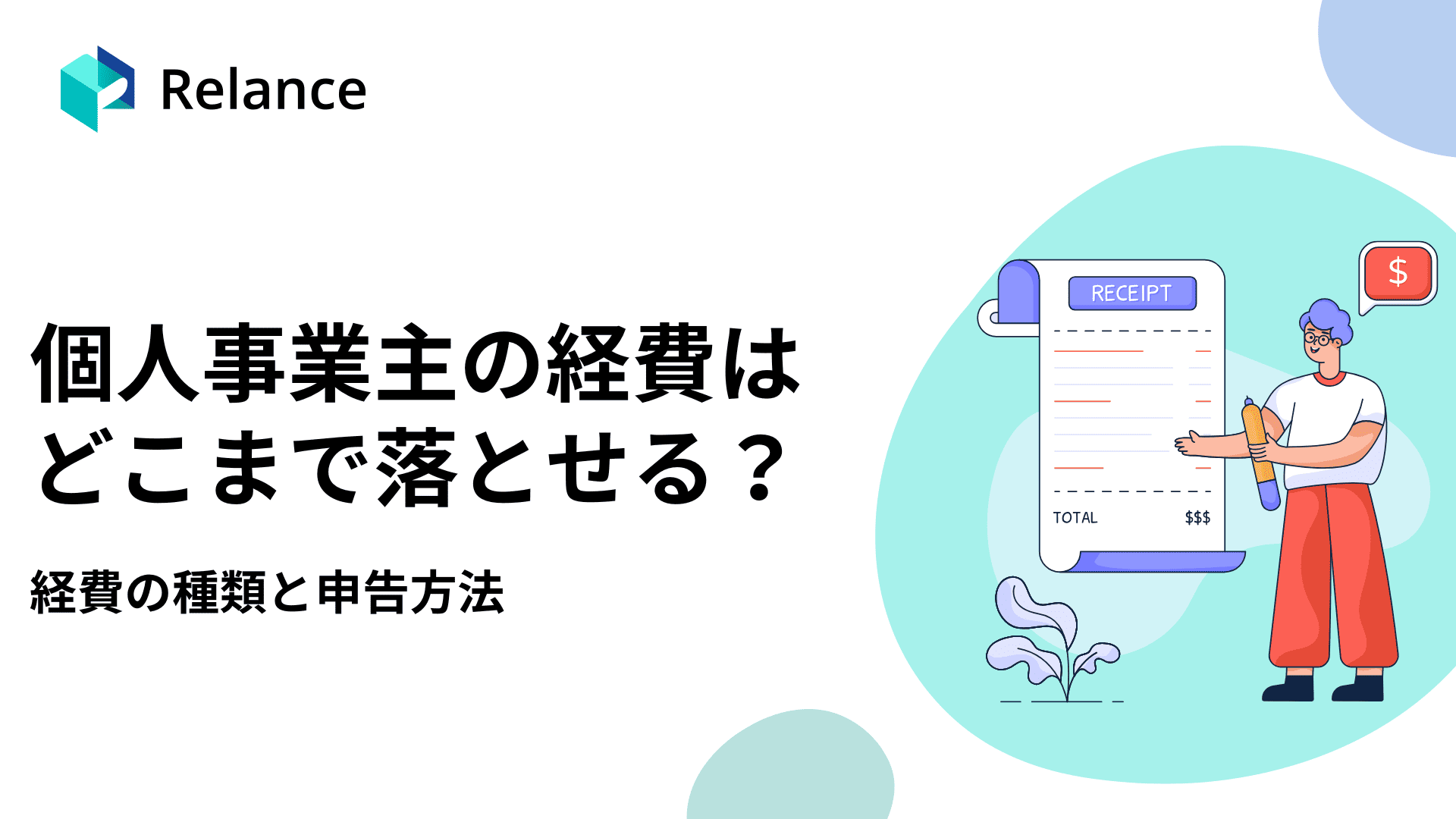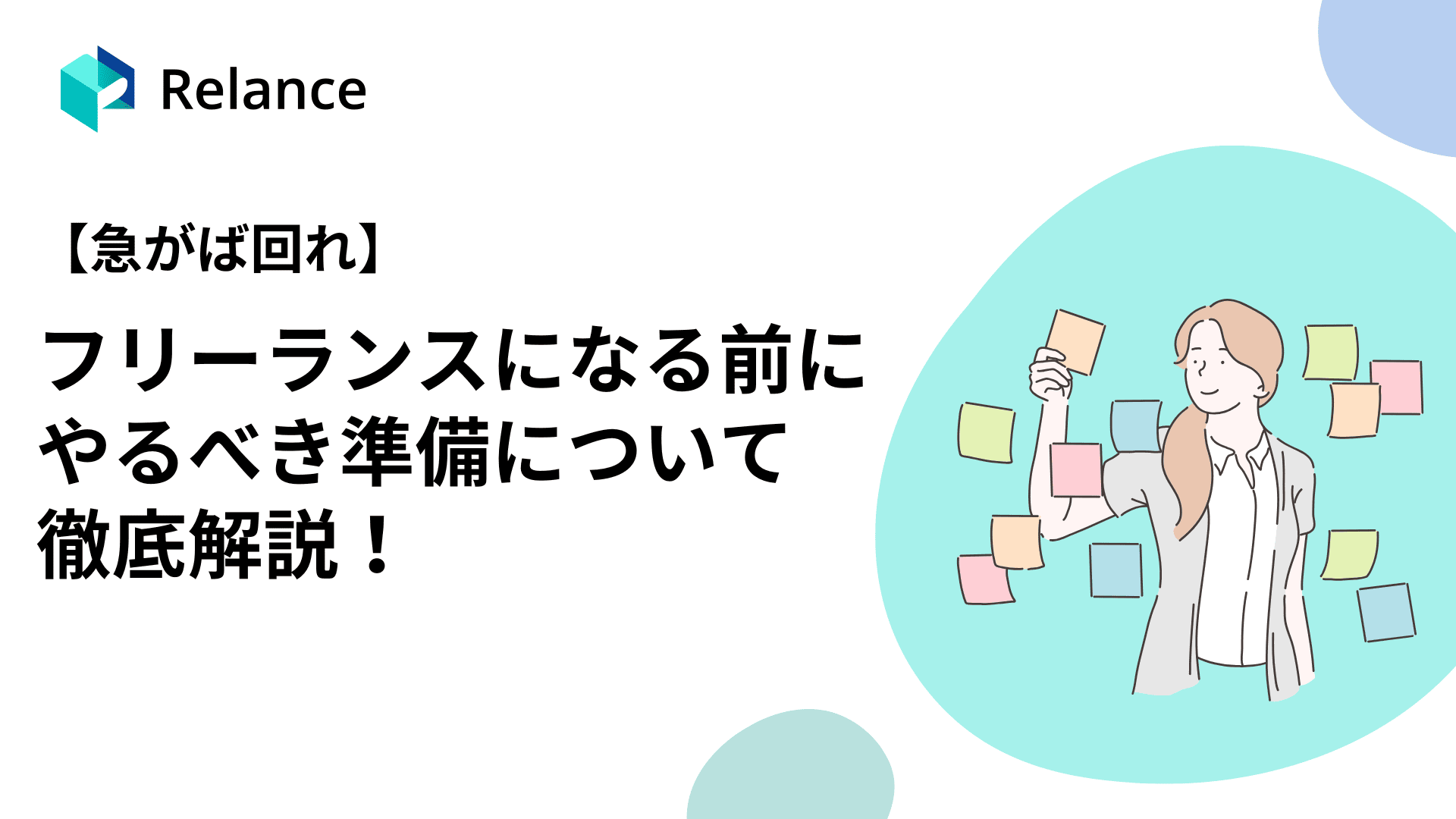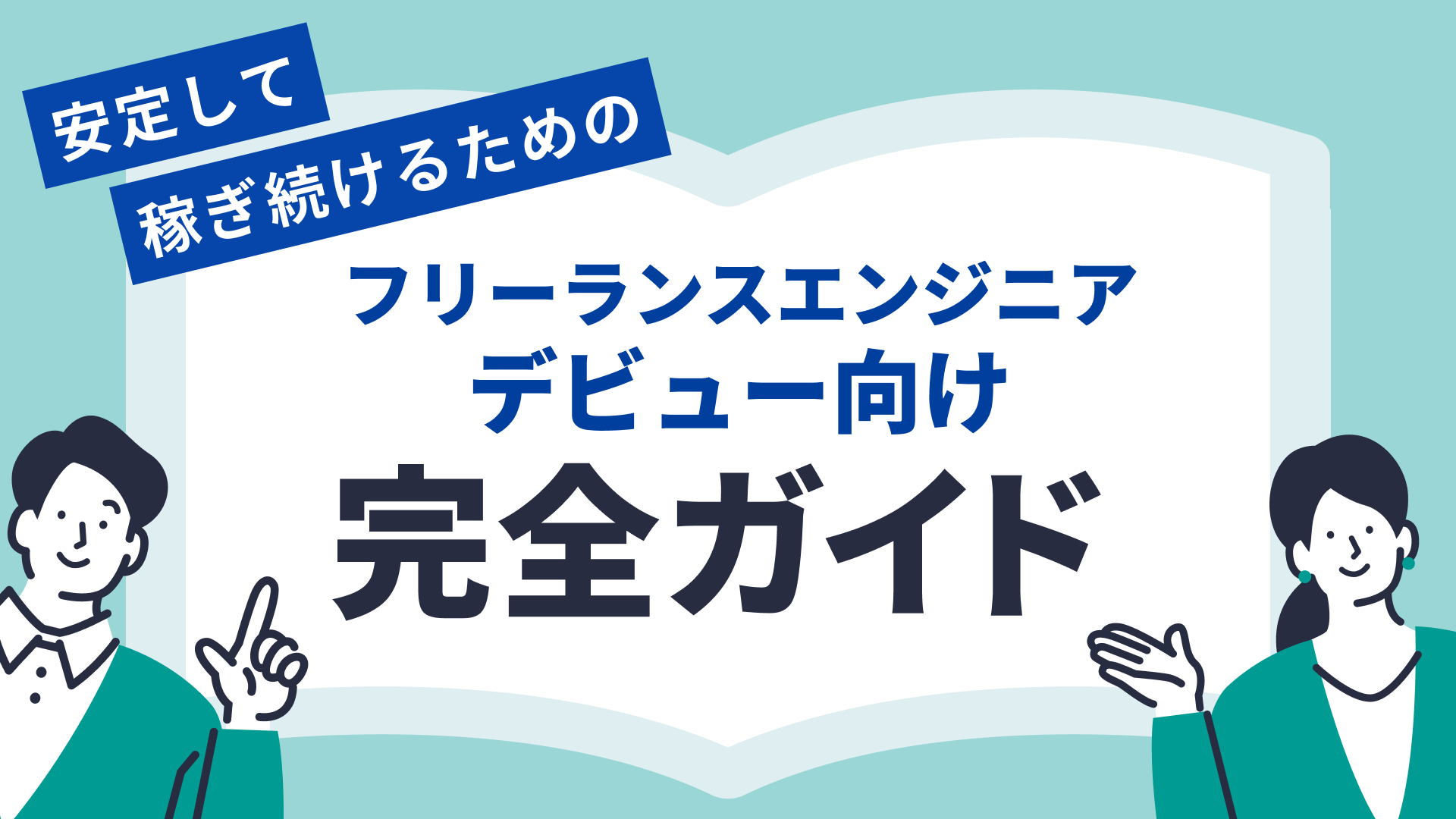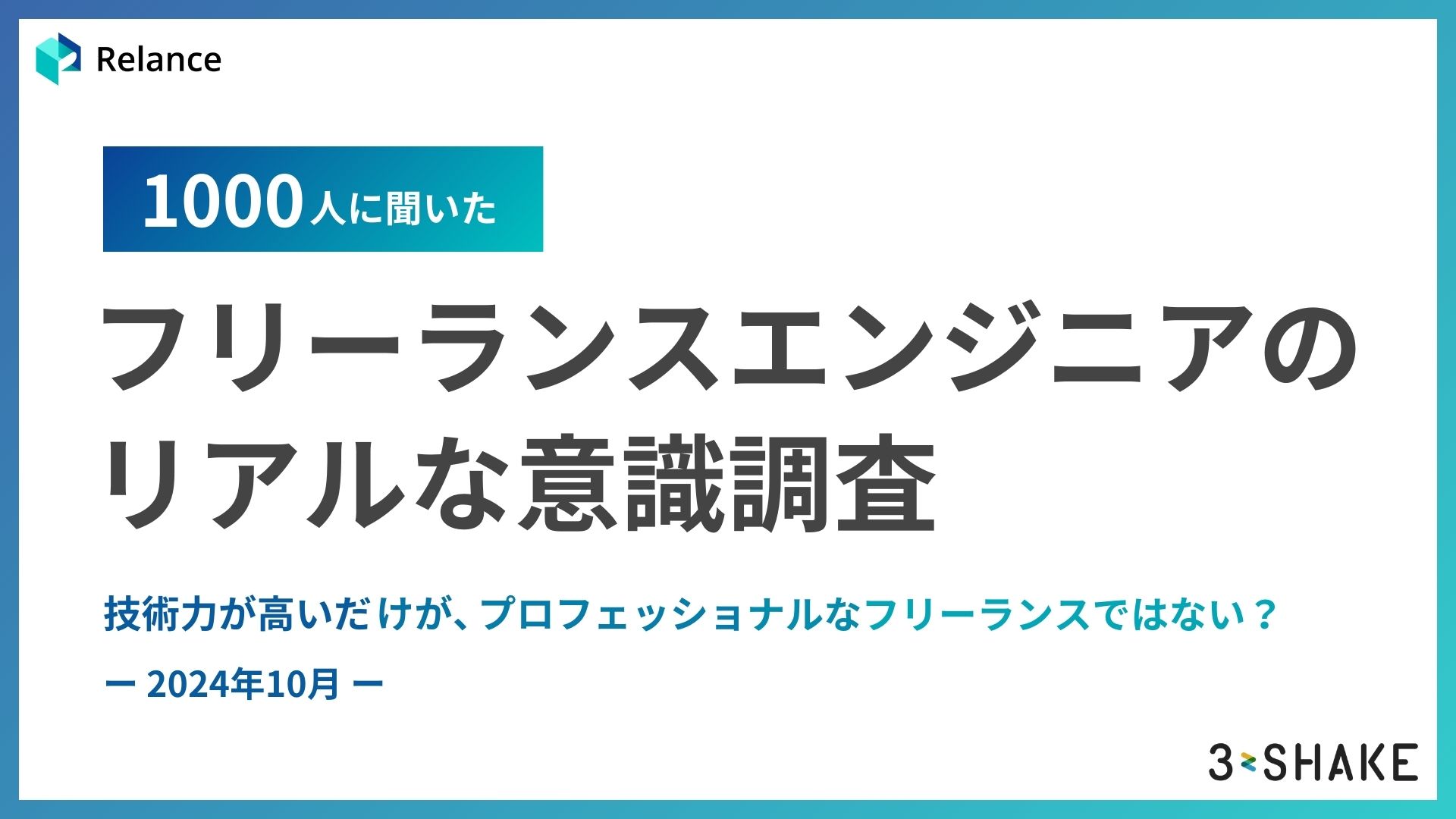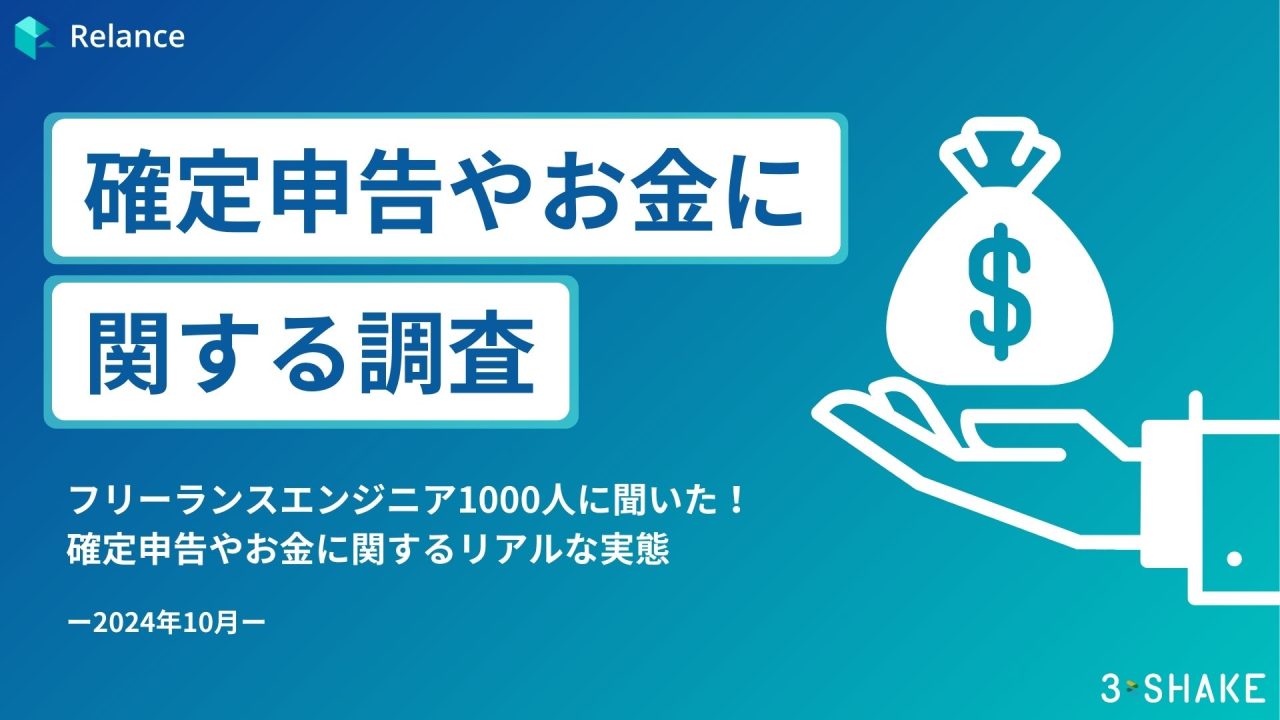フリーランスエンジニアの現実|独立前に知っておくべき光と闇を徹底解説
フリーランスエンジニアの現実|独立前に知っておくべき光と闇を徹底解説
「昇進までの道のりが長く、なかなか給料が上がらない…」
「ライフスタイルに合わせてもっと自由な時間の使い方をしたい!」
「通勤のストレスや残業の多さに悩まされている…」
会社員エンジニアとして働く中で、このような不満を抱く方は多いのではないでしょうか。
その点、フリーランスエンジニアには「好きな時間・場所で働ける」「会社員のときより年収が上がる」といったメリットがあります。
スキルや経験を十分に身につけてきたと感じ、フリーランスとして独立するのを検討している方もいることでしょう。
しかし、フリーランスについて調べてみると、「フリーランス 増えすぎ」「フリーランス やめとけ」など、フリーランスについて不安を抱くような言葉が目に入ります。会社員を辞めフリーランスとして独立するという大きな決断時には、メリットだけでなくリアルな側面についても知っておきたいものです。
フリーランスエンジニアについて事前に知っておかなければ、イメージと現実とのギャップに直面し、フリーランスになったことを後悔してしまうでしょう。
そこで本記事では、フリーランスエンジニアの現実について解説していきます。
本記事を読むことで、フリーランスエンジニアの現状から、会社員との違い、大変なことまで把握できます。フリーランスエンジニアとして活躍していく方法も紹介しているので、フリーランスとして独立することを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
フリーランスエンジニアの現実は?
まずは、フリーランスエンジニアの現実について、データをもとに見ていきましょう。
フリーランスエンジニアの平均年収、年齢層、平均稼働時間、平均継続時間などを深堀りしていきます。
自身の予想と比較しながら確認してみてください。
年収の平均は約632万円
Relanceがフリーランスエンジニア1,000人を対象に調査した「【2024年版】フリーランスエンジニア白書1000人に聞いた!フリーランスエンジニアの実態調査-2024年3月-」によると、専業フリーランスエンジニアの平均年商は約632万円でした。
「専業フリーランスエンジニアとしての年商はいくらですか?」という設問に対し、最も多かった回答が「500万円以上800万円未満」の約27.1%、ついで「300万円以上500万円未満」の約25.8%となっています。
出典:【2024年版】フリーランスエンジニア白書1000人に聞いた!フリーランスエンジニアの実態調査-2024年3月-
なお、国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、給与所得者全体の平均年収は460万円です。
また、厚生労働省の職業情報提供サイト「jobtag」によると、システムエンジニア(Webサイト開発)の平均年収は557.6万円です。
さらに、dodaの「平均年収ランキング(業種別の平均年収/生涯賃金)【最新版】」によると、ITエンジニアの平均年収は452万円(※2023年12月時点)となっています。
これらの結果から、フリーランスエンジニアの平均年商は「高い」といえるでしょう。
近年のクラウド化やDX化の煽りを受け、ただでさえエンジニアの需要が高まる中、フリーランスとなることで、より稼げる可能性が高いことが窺えます。
参考:【2024年版】フリーランスエンジニア白書1000人に聞いた!フリーランスエンジニアの実態調査-2024年3月-|Relance
参考:令和5年度 民間給与実態統計調査|国税庁
参考:システムエンジニア(Webサイト開発)|jobtag
参考:平均年収ランキング(業種別の平均年収/生涯賃金)【最新版】|doda
年齢層は30代~50代が約9割
フリーランス協会発行の「フリーランス白書2024」によると、フリーランスの年齢属性で最も多い層は「40代」です。その割合は33.2%と、全体の約3割を占めています。
その後を「50代」の24.4%、「30代」の23.7%が追っており、「20代以下」は10.5%と全体の1割ほどにしか過ぎません。
この結果から、フリーランスとして活動している人のコアな年齢層は、30代~50代であるといえるでしょう。
なお、「フリーランス白書2024」は、職種に制限を設けずフリーランス全体を対象としたアンケートです。
エンジニア以外のフリーランスも当然含まれますが、フリーランスエンジニアもおおよそ同様の結果になると想像できます。
とはいえ、フリーランスを取り巻く環境は大きく変化してきています。
実際、前年度の「フリーランス白書2023」の回答属性と比較してみると、「20代以下」のフリーランスは4.4%から10.5%と倍以上に増加しました。
昨今における働き方の多様性も作用し、今後、若い世代のフリーランスエンジニアがますます増えていくことが予想できるでしょう。
参考:フリーランス白書2024|フリーランス協会
参考:フリーランス白書2023|フリーランス協会
フリーランスの平均稼働時間は週4日・1日4.4時間
前述の「【2024年版】フリーランスエンジニア白書1000人に聞いた!フリーランスエンジニアの実態調査-2024年3月-」によると、フリーランスエンジニアとしての平均業務日数として最も多かった回答は、「5日」の26.5%でした。
「3日」の20.9%、「4日」の17.5%、「2日」の15.7%と続いており、稼働日数としては「週4日」が平均的なようです。
なお、1日の平均業務時間として最も多い回答は「5~10時間未満」の約34.8%であり、「3~5時間未満」は約33.0%、「1~3時間未満」は約25.4%という結果でした。
平均すると、1日4.4時間ほど稼働しているフリーランスエンジニアが多いようです。
出典:【2024年版】フリーランスエンジニア白書1000人に聞いた!フリーランスエンジニアの実態調査-2024年3月-
フルタイムで勤務する会社員と比較すると、ゆとりのある働き方といえるのではないでしょうか。
なお、フリーランスエンジニアが抱える案件数としては、「2~3件」が平均的な数字となります。
参考:【2024年版】フリーランスエンジニア白書1000人に聞いた!フリーランスエンジニアの実態調査-2024年3月-|Relance
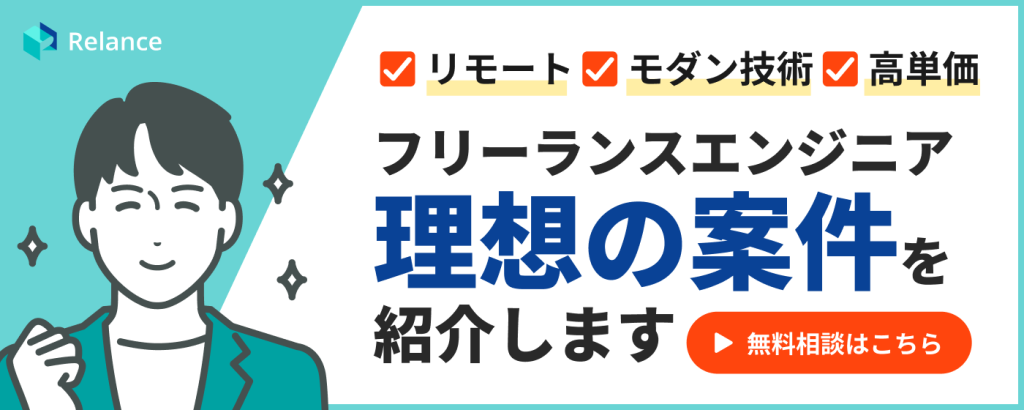
フリーランスエンジニアに関する市場動向は明るい
ここまで、フリーランスエンジニアの「現実」について、データをもとに解説しました。
では、今後の市場動向としては、どのように予想されるのでしょうか?
結論から申し上げますと、フリーランスエンジニアに関する市場動向は明るい、といえます。
- フリーランスエンジニアは増加傾向にある
- フリーランスエンジニアの需要は今後も高まっていく
上記2つの観点から、フリーランスエンジニアの市場動向について見ていきましょう。
フリーランスエンジニアは増加傾向にある
フリーランスは2020年から2021年にかけて急増しており、今後も増加していくことが予想されます。
ランサーズの「新・フリーランス実態調査 2021-2022年版」によると、2021年10月時点でフリーランスは約1580万人いることが報告されています。これは労働人口の22.8%です。
出典:新・フリーランス実態調査 2021-2022年版|ランサーズ
さらに同調査では、副業をしたことがない人のうち6割以上の方が「副業をしてみたい」と回答していました。また、今後習得したいスキルとしてプログラミングスキルが多く挙げられており、現在は政府がリスキリングを支援する方針も打ち立てています。
今後、フリーランスエンジニアはますます増えていくことが見込まれるでしょう。
とはいえ、フリーランスエンジニアが増加する見込みであることは、競り合う相手が増えることを指します。
そのような環境で案件を獲得していくためには、知識や技術といったスキルはもちろん、生存戦略に基づいた自己研磨も欠かせません。
参考:新・フリーランス実態調査 2021-2022年版|ランサーズ
フリーランスエンジニアの需要は今後も高まっていく
フリーランスエンジニアの需要は、今後ますます高まっていくでしょう。
経済産業省の資料「IT分野について」によると、IT人材の不足は、2020年の約37万人から、2030年には約79万人にも拡大するとされています。
IT化が進む現代においてエンジニアの需要は高まっており、需要に対して人材は今後ますます不足していくと予想されます。
企業におけるクラウド化、DX化の動きはさらに加速しており、生成AIを筆頭に、数年前とはまた別の課題も増えてきているのが現状です。
サイバー攻撃は複雑化しており、情報セキュリティの脅威に対抗し得る技術もますます必要とされてきています。
このように、エンジニアが不足しているという背景、IT化が加速している現状、セキュリティなどあらゆる理由から、 将来的にもフリーランスエンジニアの需要は高いといえるでしょう。
知識・スキルをしっかりと身につけ、最新の情報を敏感にキャッチアップし、地道に経験を積んでいけるフリーランスエンジニアであれば、今後の見通しも明るいはずです。
参考:IT分野について|経済産業省 商務情報政策局 情報処理振興課
多くのフリーランスエンジニアが現実で直面する苦労5つ
フリーランスエンジニアとして活動していく際、押さえておくべきポイントがあります。
- 案件を自身で獲得する必要がある
- 仕事の全責任は自分にある
- エンジニア以外の仕事も必要
- 会社員のような保証がない
- 社会的信用が低い
これらのポイントをしっかりと理解していなければ、「こんなはずではなかった…」という後悔にもつながりかねません。
多くのフリーランスエンジニアが直面する「現実」について、それぞれ詳細を確認していきましょう。
案件を自身で獲得する必要がある
フリーランスは自分で仕事を獲得していく必要があります。
いくらエンジニアとしての十分なスキルを持っていて案件をこなせる自信があっても、そのスキルがクライアントに伝わらなければ、案件の獲得にはつながりません。
営業活動の経験がないエンジニアは非常に多いです。最初は不慣れであり、思うように案件を獲得できないこともあるでしょう。うまく案件が獲得できないと低単価な案件を受注することになり、収入が落ち込むなど不安定にもなってしまいます。
フリーランスとして活躍していくためには、エンジニアとしてのスキルだけではなく、営業力やコミュニケーションスキルなど多様なスキルが求められるのです。
さらに、フリーランスは案件ごとの契約をするため、コロナ禍などの不況に陥ったときには案件が少なくなってしまい、仕事が受けられなくなるリスクもあるでしょう。
仕事の全責任は自分にある
フリーランスは会社員と比べ、仕事や働き方など自分で決められることが多くあり自由である分、責任もすべて自分にあります。
会社員の場合、会社を休んだときや仕事でミスをしたときには、上司や同僚が助けてくれることもあるでしょう。
その点フリーランスの場合は、すべて自分で解決する必要があります。ミスや休んだときに助けてくれる同僚もいません。
ミスなどによってクライアントからの信頼を失ったときには、更新もなく契約終了となる可能性も考えられます。
たった1つのミスが原因で、案件の解約へと至ってしまうこともあるかもしれません。
また、自己管理能力の有無も重要なポイントです。
フリーランスエンジニアには、体調管理はもちろん、納期の厳守などタスク管理・スケジュール管理も求められます。
自己管理能力がなければ、収入そのものを失ってしまうことも考えられるでしょう。
自分を律し、心身を強く保つことも必要なのです。
エンジニア以外の仕事も必要
フリーランスは、エンジニアとしてのコア業務だけでなく、先ほど説明した営業に加え、事務や税務などさまざまな仕事をしなければいけません。
会社員の場合、源泉徴収制度により、会社が個人に代わって納税をしてくれます。会社が給与額をもとに所得税や住民税、社会保険料などを算出し、給与から天引きする制度です。
しかしフリーランスは、自分で確定申告をおこない納税する必要があります。確定申告をおこなうためには、税務の知識や会計スキルが欠かせません。
税金の内容をしっかりと理解することは難しいですが、確定申告のミスはペナルティにつながり、最悪の場合は税務調査が入ることもあるでしょう。そのため、納税額を正確に計算することが求められます。
領収書の保管や経費計上、控除の手続きなど、おこなうべきことは山ほどあります。
税務に対する正しい知識がなければ、節税もできません。
営業に関しても、コミュニケーション能力が求められるだけでなく、案件獲得のための提案資料やポートフォリオなどをすべて自分1人で作成し用意する必要があります。
加えて、フリーランスには、契約の手続きといった細々とした事務作業なども日常的に発生します。
このように、フリーランスとしてやっていくためには、エンジニアとしての技術力以外のスキルも必要となるのです。
会社員のような保証がない
フリーランスには、福利厚生や退職金がありません。
フリーランスは厚生年金を支払わないため、将来得られる年金の額が会社員より大きく減り、また退職金もないため、老後への不安を抱きやすいものです。
会社員であれば、社会保険として万が一の場合に備えた雇用保険や労災保険などの保証にも守られています。ほかにも、交通費や学習費、住宅補助が支給されたり、場合によってはウォーターサーバー代や社食代など福利厚生とは認識していないようなサポートも受けていることもあるでしょう。
このようにフリーランスは、保証の面でも弱い立場にあります。
社会的信用が低い
フリーランスは会社員と比較して社会的信用が低く、一般的にクレジットカードやローン、賃貸の審査に通りにくくなるものです。
実際、前述のアンケートにおいても、フリーランスのデメリット・不満な点として「社会的信用が低い(クレジットカードやローンの審査など)」が最も多い割合で挙げられています。
出典:【2024年版】フリーランスエンジニア白書1000人に聞いた!フリーランスエンジニアの実態調査-2024年3月-
会社員の場合、在籍の証明さえできれば、会社という看板から信用を得られるケースも多いでしょう。
その点、フリーランスは誰でもフリーランスとして名乗れるため、事業を本当におこなっているのか、どのような事業内容なのかといった透明性が担保されにくいです。
フリーランスは社会に合わせて働けない人、という悪いイメージを持つ方も、残念ながら少なくありません。働き方の多様性によりフリーランスの認知度は上がってきているものの、社会的信用は会社員に比べてまだまだ低いのが現実です。
年収も安定していないために与信審査に通りにくい、という点もデメリットです。フリーランスは案件ごとに報酬を得るため、月によって収入が変動することが往々にしてあります。
希望に沿った単価の案件が獲得できなかったときや体調不良などで案件数を減らしたときには、収入が下がり滞ってしまうことが考えられるでしょう。そのような懸念から、審査が通りにくい事情があるのです。
また、上記のアンケートでは、「将来の社会保障が少ない」ことをデメリットとして挙げるフリーランスエンジニアも多くいました。
社会保険や年金の面を見ても、フリーランスは会社員と比較し不安定であることを覚悟しておかなければなりません。
参考:【2024年版】フリーランスエンジニア白書1000人に聞いた!フリーランスエンジニアの実態調査-2024年3月-|Relance
フリーランスエンジニアとして活動する魅力
ここまで、フリーランスエンジニアが直面する厳しい現実についてお伝えしてきましたが、もちろん大変な面だけではありません。
フリーランスエンジニアとして活動していく魅力も多々あります。
- 働く場所や時間を調整しやすい
- 能力次第で収入が上がる
- 人間関係から開放されやすい
- 節税対策がしやすい
- 定年退職がない
上記5つの魅力について、詳しく見ていきましょう。
働く場所や時間を調整しやすい
フリーランスエンジニアとして活動する魅力の1つとして挙げられるのは、「働く場所や時間を調整しやすい」ことです。
実際、Relanceの調査においても、フリーランスになって感じたメリット・満足している点として「働く時間に縛られない」が44.8%、「働く場所に縛られない」が44.7%と上位を占めています。
近年、新型コロナウイルスの影響を受け、働き方の多様性も広がってきました。
その1つが「リモートワーク」です。
とくにフリーランスはリモートで働く傾向が強く、さらにエンジニアはリモートワークと相性の良い職種といえます。
上記の調査でも、「出社・リモート勤務の配分で当てはまるものを教えてください」という問いに対し、「基本的にリモートワーク」という回答は29.52%でした。
「リモートでの業務多め・一部出社」は21.07%、「クライアント企業に出社多め・一部リモート」は30.72%です。
リモートワークを導入しているフリーランスエンジニアが8割を超えることがわかりました。
出典:【2024年版】フリーランスエンジニア白書1000人に聞いた!フリーランスエンジニアの実態調査-2024年3月-
前年度の調査と比較しても、リモートの割合は3%増加しています。
Relanceで扱っている案件についても、リモート案件が非常に多いです。
好きな時間に働くことで、プライベートの時間を確保したり、家事・育児との両立もしやすかったりと、享受できるメリットは倍増するでしょう。リモートであれば出社する必要もないため、通勤のストレスからも解放されます。
参考:【2024年版】フリーランスエンジニア白書1000人に聞いた!フリーランスエンジニアの実態調査-2024年3月-|Relance
能力次第で収入が上がる
フリーランスは、スキルが収入に直結します。高いスキルがあれば、フリーランスエンジニアは、会社員エンジニアよりも年収が上がる可能性も十分にあるでしょう。
実際、「【2024年版】フリーランスエンジニア白書1000人に聞いた!フリーランスエンジニアの実態調査-2024年3月-|Relance」でも、フリーランスエンジニアになってから収入が上がったと答えた人は59.52%と過半数でした。
上がった収入の平均値は約490万円、中央値は約500万円と、かなりの収入増が見込まれることも窺えます。
フリーランスエンジニアの場合、スキルさえあれば会社が獲得する案件よりも高い単価の仕事を獲得可能です。
とはいえ、スキルや経験がなければ、会社員時代よりも収入が下がる可能性ももちろんあります。
フリーランスエンジニアは、良くも悪くも自身のスキル・経験がそのまま収入にあらわれる働き方といえるでしょう。
自分のエンジニアとしてのスキルや実績をしっかりと積み上げ、それを適切にクライアントにアピールできれば、会社員時代は考えられなかったような高単価の案件を獲得できるでしょう。年収をさらに高めていける点が、フリーランスエンジニアの魅力です。
参考:【2024年版】フリーランスエンジニア白書1000人に聞いた!フリーランスエンジニアの実態調査-2024年3月-|Relance
人間関係から解放されやすい
フリーランスは個人で活動するため、社内の煩わしい人間関係から解放されます。
会社員の場合、上司や同僚との人間関係に悩まされることも多いでしょう。上司からの評価に不満を抱いたり、同僚との付き合いで自分の時間が削られたりもします。
その点、フリーランスは社内の人間ではなく、個人で活動するため、上司・同僚との飲み会といった業務を超えての付き合いは調整可能です。
とはいえ、人間関係から完全に解放されるわけではありません。エンジニア案件に関わる以上、チーム開発なども当然あり、チームメンバーとの人間関係構築は不可欠です。
また、案件の長期継続のためには、クライアントと良い関係性を築くことも求められます。
フリーランスエンジニアは、会社員と比較し苦手な人との関わりを少なくできるなど、密な関係の中でのストレスが和らぐ部分があります。一方で、フリーランスとしての活動のために、人間関係構築に努める必要もあることは頭に入れておきましょう。
節税対策がしやすい
フリーランスは、納税において経費の計上ができるため、節税対策がしやすいです。
フリーランスは会社員と違い、確定申告などの税務処理を自分でおこないます。会社員の場合、課税所得を求めるときの給与控除は給与に応じて定められていますが、フリーランスであれば事業に関わる費用を経費として申請でき、節税が叶います。
経費は自分である程度コントロールできるため、うまく活用すれば会社員よりも高い節税効果を得られるでしょう。
たとえば、業務のみに使用するパソコンのネット回線やスマートフォンの使用料、打合せに出向くための交通費などは経費対象ですし、自宅で作業しているのなら家賃や光熱費なども家事按分にて経費計上できます。
会社と折半できない分、社会保険料などの負担は増えてしまうものの、上手にやりくりすれば、会社員時代よりも手取りが増えるケースもあるのです。
ただし、税務に関する正しい知識がないと、賢く節税できない場合や、逆に脱税行為になってしまうこともあります。
しっかりと知識を入れた上で、賢く正しい節税対策を講じましょう。
Relanceでは、フリーランスエンジニア約1000人を対象に関する調査を行いました。フリーランスエンジニアの確定申告やお金に関するリアルな実態を知りたい方はぜひご活用ください!
⇒フリーランスエンジニア1000人に聞いた!確定申告やお金に関する調査をダウンロードする(無料)
定年退職がない
フリーランスには、基本的に定年退職がありません。
会社員の場合、一定の年齢に達すると定年を迎え、再雇用されない限りは、どんなに健康でやる気があっても必ず退職するときが来ます。仮に再雇用が叶った場合も、給料は現職時より下がってしまうのが一般的です。
一方フリーランスの場合は、定年退職の制度そのものが存在しないので、働くための体力やスキルがある限りは、年齢に制限なく仕事を続けられます。
年金など将来の保障に不安があるフリーランスにとって、どれだけ長く続けられるかは、死活問題です。
できるだけ長く働き続けるために、情報のキャッチアップやスキルの研磨は絶えずおこなっていきましょう。
フリーランスとして安定的に仕事をするには?
ここまで、フリーランスエンジニアとして働いていくにあたって大変なこと、魅力的な点についてお伝えしました。
では実際に、困難を乗り越え、メリットを最大限に享受しながら活躍していくためには、どうすればよいのでしょうか。
フリーランスで安定して案件を獲得していくポイントを、3つご紹介します。
- フリーランスエージェントを使う
- 技術力以外のスキルも磨く
- 人脈を大切にする
それぞれ詳しく見ていきましょう。
フリーランスエージェントを使う
フリーランスエージェントとは、営業活動を代行し、案件を紹介してくれるサービスのことです。
フリーランスエージェントは、自分の希望やスキル、実績に合った仕事を紹介してくれるため、自分にぴったりの仕事を獲得できます。フリーランスエンジニアは営業に不慣れな方も多く、また営業には時間と手間がかかるものです。エージェントを利用することで、営業に割く時間を省いて自身はコア業務に集中できるため、大きな助けとなるでしょう。
福利厚生やサポートの手厚いエージェントも少なくありません。
Relanceでは、エンジニア一人ひとりに寄り添い、それぞれのスキルや希望に見合う案件をご紹介しています。
高単価報酬の案件も多く扱っており、利用者の平均年収は1,000万円以上です。
そのほかリモート案件や、最新技術を用いたモダン案件も豊富に扱っています。
キャリアアップ支援などサポート体制も整っているので、気になる方はぜひ活用をご検討ください。
参考:Relance
技術力以外のスキルも磨く
フリーランスエンジニアとして活動していくには、当然高い技術力が求められますが、必要なのはそれだけではありません。
長く生き残るフリーランスエンジニアの多くは、高いビジネススキルも身につけています。
ビジネススキルとは、たとえばクライアントやチームメンバーと適切にコミュニケーションをとるスキルや、タスクやスケジュールを管理する力、プロジェクトを円滑に推進するスキルなどです。
フリーランスエンジニアとして年齢や経験値が上がっていくにしたがって、マネジメント能力なども求められるようになります。
それらのスキルと技術力とを併せ持つフリーランスエンジニアは、長く、また広く重宝されることでしょう。
汎用的なスキルの高さも重要と心得て、総合的に身につけていきましょう。
人脈を大切にする
案件を獲得するための経路として、人脈を作っておくことも大切です。
実際、フリーランス協会による「フリーランス白書2024」では、「直近1年間で仕事獲得に繋がったことのあるもの」への回答として、「人脈(知人の紹介含む)」が61.6%と最も多い割合となっています。
また、「過去・現在の取引先」という回答も58.9%と多く、案件獲得において人脈がいかに大事かが窺える結果となりました。
同調査の「最も収入が得られる仕事の獲得経路」においても、「過去・現在の取引先」の32.7%と「人脈」の27.9%が過半数を占めています。
過去や現在の取引先から紹介してもらうためには、スキルを成果で示し、コミュニケーションを通して信頼関係を築くことが大切です。
現在のクライアントとの関係を良好に保つことは、フリーランスとして活動していく上で欠かせません。
また、同業のフリーランス仲間から仕事を紹介される可能性もあります。
セミナーや交流会に参加し人脈を広げたり、SNSをうまく活用したりなど、積極的に新しい人脈を獲得していくようにしましょう。
まとめ
本記事では、これからフリーランスになるか検討している方に向けて、「フリーランスエンジニアの現実」について解説してきました。
フリーランスは会社員より収入が上がる傾向にあり、将来性は高いです。
フリーランスには、収入が不安定になりやすい、すべてが自己責任になる、福利厚生がない、社会的信用が低いなど大変なところがあるのは事実です。
一方で、自由な働き方を実現できる、人間関係から解放されやすいなどの魅力もあります。
フリーランスとして大変なところを乗り越え、安定して活躍する方法もご紹介したので、ぜひ実践してみてください。
本記事をもとに、フリーランスの現実を知った上で、フリーランスとして独立するかどうか、しっかりと考えていきましょう。
無料で高単価案件を紹介してもらう
関連記事