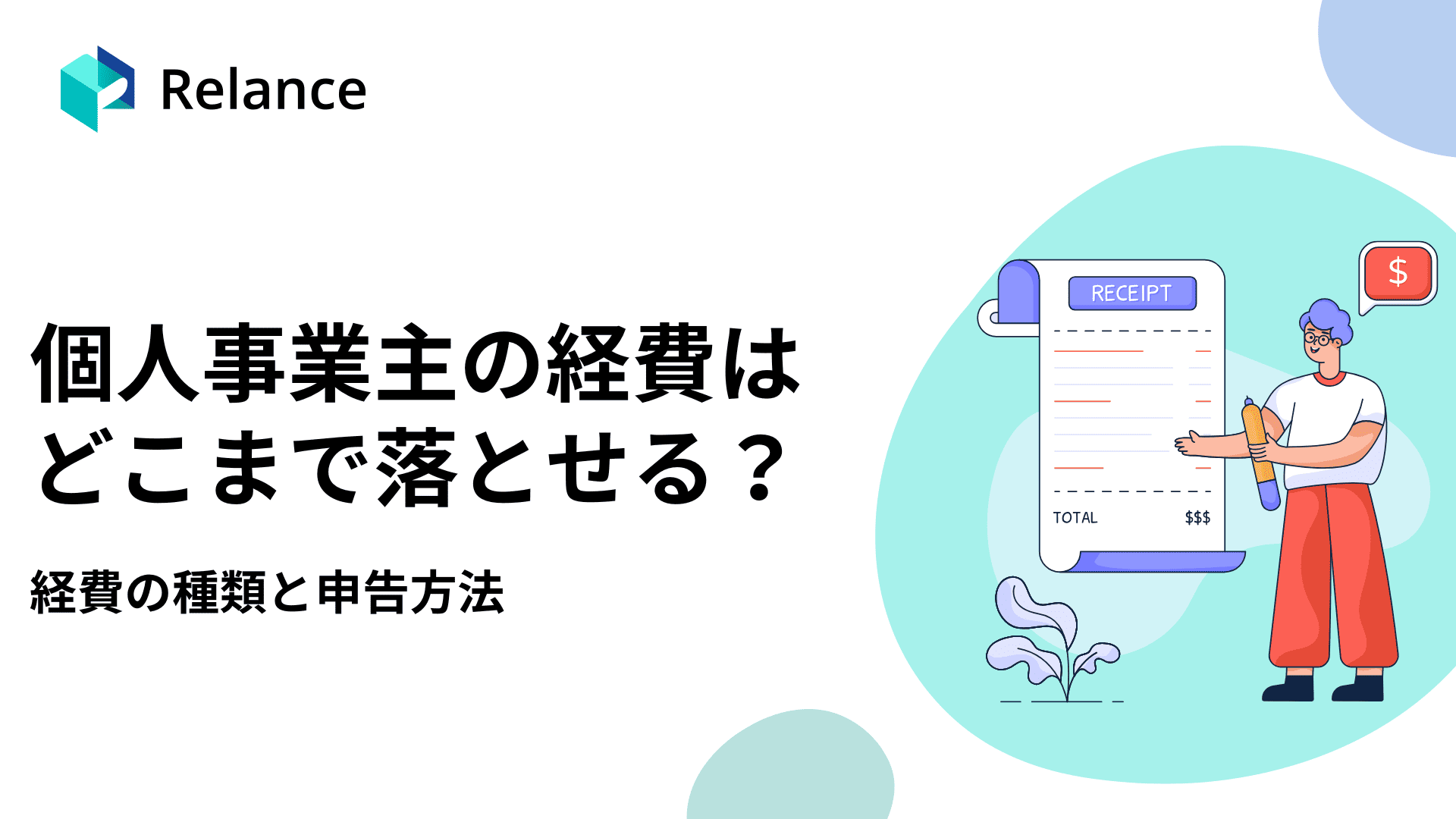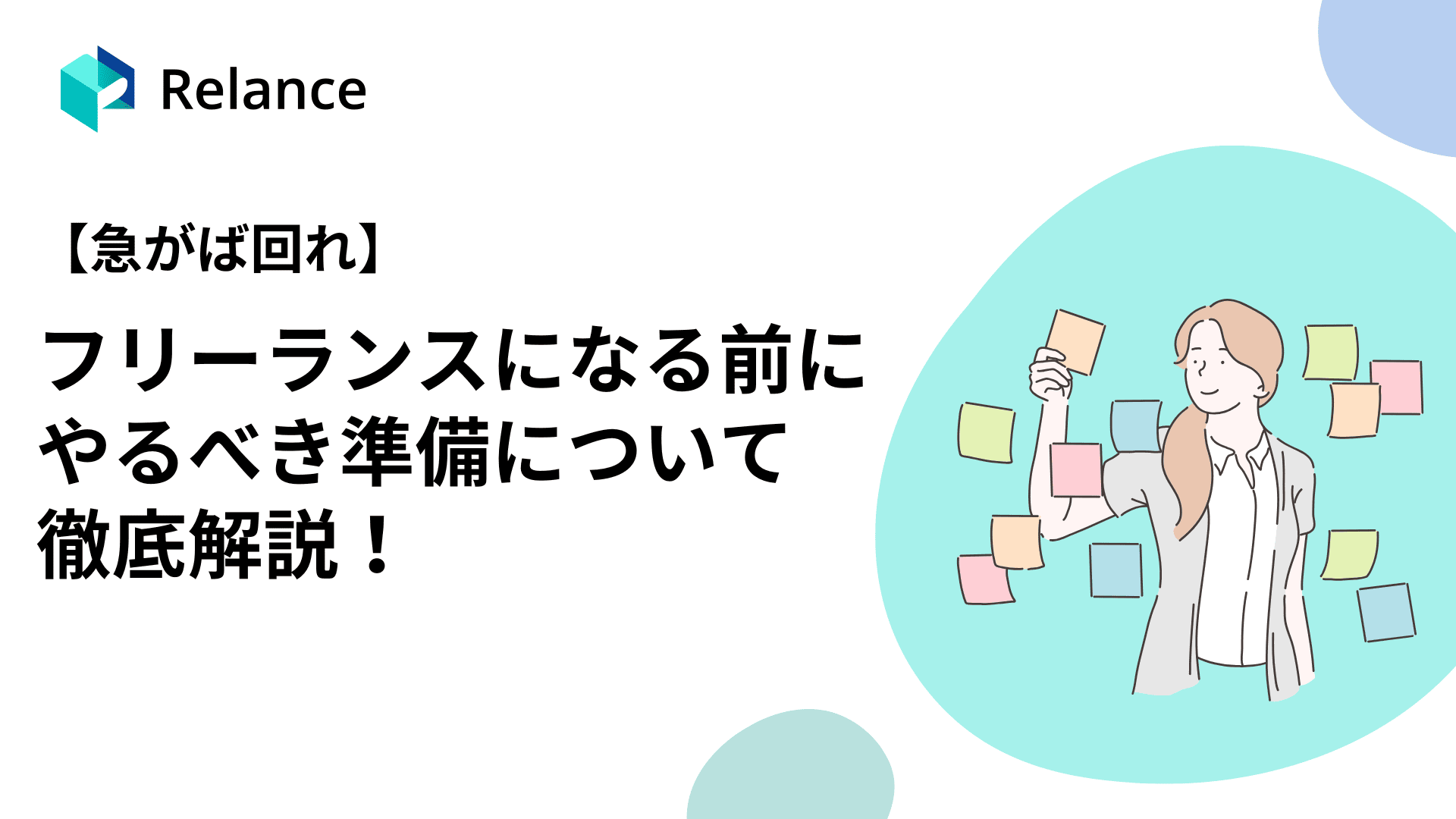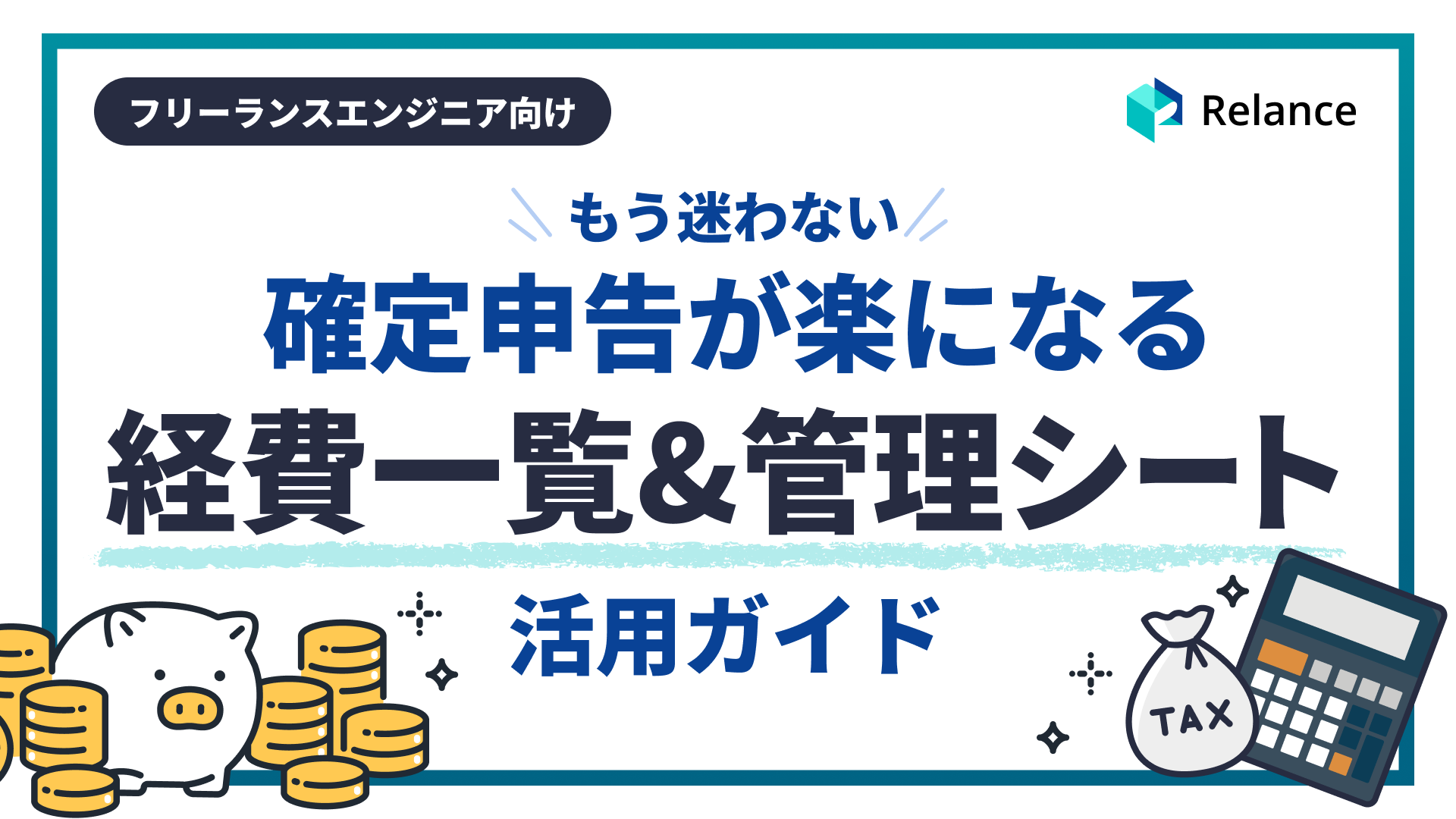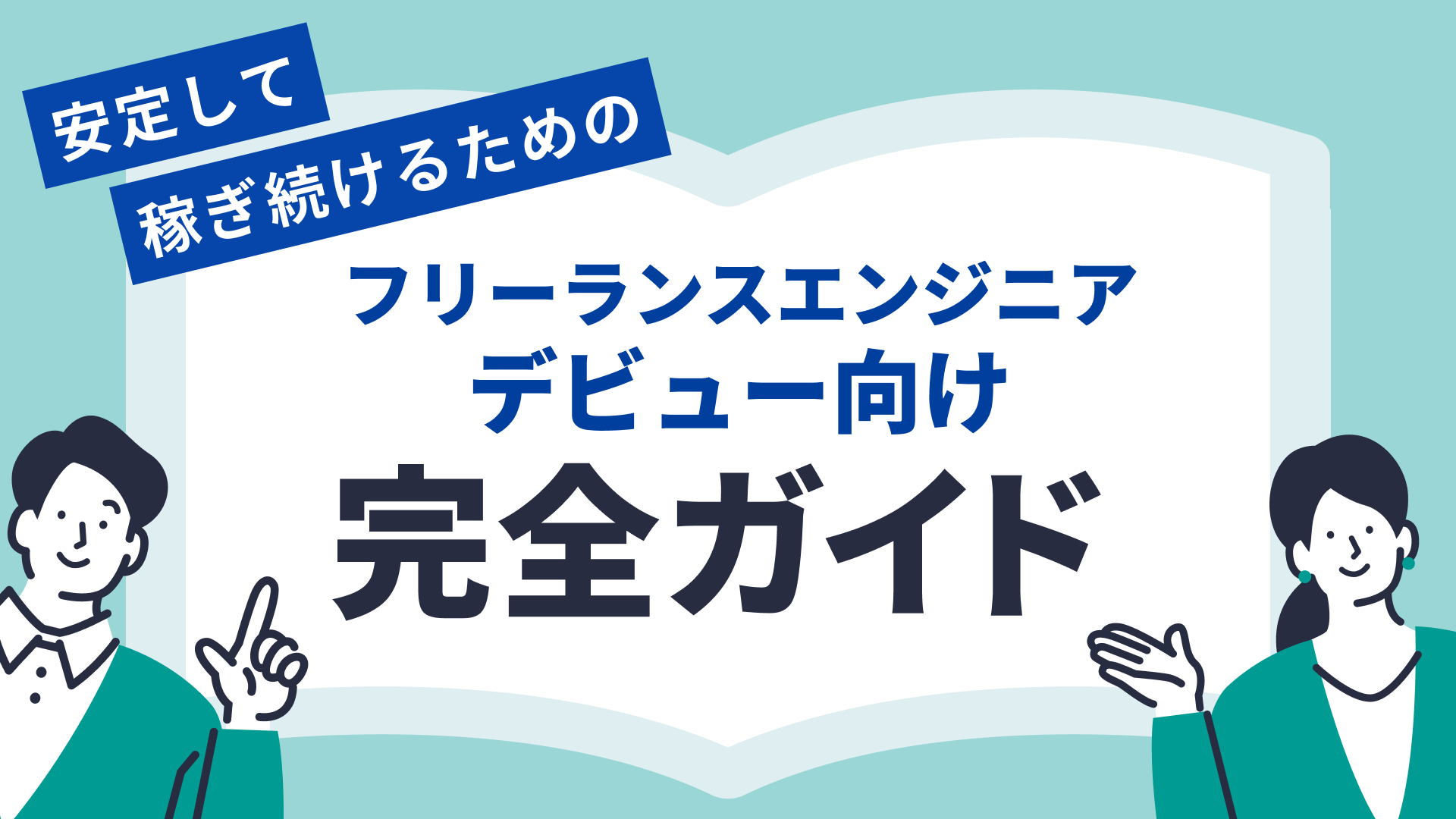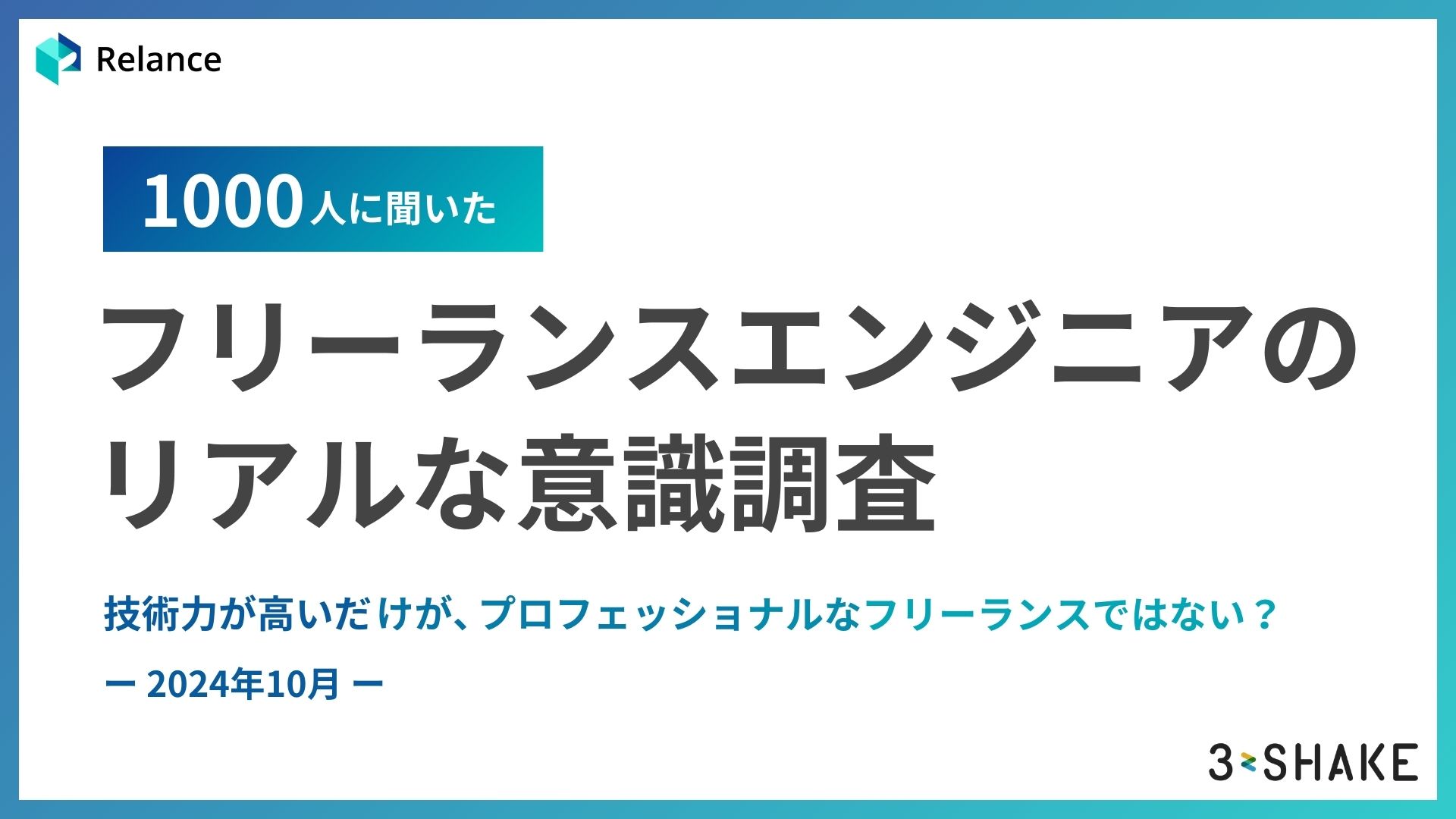エンジニアが独立するベストなタイミングは?失敗しないための考え方を解説
年収アップや柔軟な働き方を実現するため、エンジニアとしての独立を前向きに検討しているものの、独立のタイミングや準備について悩む方も多いのではないでしょうか。
本記事では、エンジニアが独立するベストなタイミングや、独立の利点、懸念点とその対策について詳しく解説します。また、独立前に必要な具体的な準備についても説明するので、フリーランスエンジニアとして独立を考えている方はぜひご参考にしてください。
Relanceは、エンジニア目線でスキルや経験にマッチした高単価案件をご紹介しております。
メルマガで案件の最新情報を配信しているので、ぜひ登録してください!
⇒Relanceの案件速報を受け取る【無料】
目次
エンジニアが独立する3つのタイミング
エンジニアとして独立するには、好きなタイミングで独立することができます。しかし、独立をするタイミングを誤ってしまうと、仕事を受けることができず、現在よりも年収が下がってしまう可能性も高いです。
エンジニアの方が独立するおすすめのタイミングとして、3つのタイミングがあります。
・継続的に案件獲得ができる見通しが立ったとき
・一人前のスキルが身についたとき
・資金にゆとりができたとき
1つずつ確認していきましょう。
継続的に案件獲得ができる見通しが立ったとき
エンジニアとして独立する上で、最も不安なのは収入面でしょう。そのため、エンジニアとして独立するタイミングとして、継続的に案件獲得ができる見通しが立ったときが良いと言えます。
継続的に案件獲得ができると見込めるには、独立する前に副業として案件獲得などをおこなっておくことが大切です。実績を積んでおくことで、単発の依頼を受けやすくなったり、同じクライアントから継続的に案件を受注できる可能性が高くなります。
エンジニアとして独立する前に案件を受けておくことで、案件獲得や業務の流れについて理解を深めることができるため、独立後の業務をイメージしやすいです。
初めて案件を獲得する場合は、クラウドソーシングサイトの利用や営業をおこなう必要があります。実績がない状態では、単価が低くなってしまう可能性がありますが、案件を受けて実績を積んでいき、高単価案件に応募してみましょう。
また、友人や知人の紹介などで案件を獲得できる可能性もあります。知り合いから案件を受けられる見込みがある場合には、実績を積むことができますし、収入面の不安も少なくなるでしょう。
近年では、SNSの普及に伴い、SNSから案件獲得をするエンジニアも増えてきました。これからエンジニアとして独立しようと考えている場合には、SNSを利用して実績をアピールすることもおすすめです。
Relanceでは、担当者から評価されやすいスキルシートの書き方やフォーマットを提供しております。
案件獲得に不安を抱えているフリーランスエンジニアの方はぜひご活用ください!
⇒【すぐに使える!】案件獲得につながるスキルシートをダウンロードする(無料)
一人前のスキルが身についたとき
エンジニアが独立するタイミングとして、一人前のスキルが身についたときというのもポイントです。独立後のエンジニアは、スキルレベルが年収に直結すると言えます。特にPMなどの上流工程は高単価であることが多く、企業で勤めている間に上流工程の経験をしておくことで、独立後にも上流工程の案件を獲得しやすくなります。
場合によっては、1つの案件でWebサービスとアプリの連携など、複数の分野に関わる可能性もあります。そのため、1つの分野に特化することも大切ですが、多くの分野の経験を積んでおくこともエンジニアが独立する上で重要なスキルとなるでしょう。
資金にゆとりができたとき
エンジニアが独立するタイミングの3つ目として、資金にゆとりができたときが挙げられます。
実績が乏しく継続的に案件獲得ができる見通しがあまり立っていない場合には、収入が少なくなってしまう可能性があります。そのため、エンジニアとして独立するタイミングとしては、収入が不安定になっても生活できる資金を準備できたときが良いです。
具体的には、半年から1年程度は収入がなくても生活できる程度の資金があると安心でしょう。
エンジニアが独立するために必要な経験年数の目安は3年
エンジニアとして独立を考える際の、一般的な目安となる実務経験年数は3年です。3年程度の実務経験があれば、実務上必要なスキル・知見が身についているため、企業から安心して依頼してもらいやすくなります。
より具体的には、3年程度の経験を積むことで、システム開発の全体像が見え、プロジェクトの進め方も理解できるようになります。また、開発で重要な「オブジェクト指向」への理解や、インフラの知識も備わってきます。加えて、実務を通じて、現場での問題解決能力や顧客とのコミュニケーション能力も培われているでしょう。
3年の実務経験があればこうしたスキルセットを持つことができ、フリーランスとしても案件を1人で遂行できるようになっているはずです。そのため、独立する前には最低でも会社員として3年の下積みを積むとよいでしょう。
5年以上経験していると参画できる案件の幅が広がる
エンジニアとして5年以上の実務経験を積むことで、システム開発における幅広い工程を経験することができ、スキルや経験も十分に深まっているため、より多様な案件への参画機会が広がります。
たとえば、開発経験が5年ある場合、Pythonなど特定の言語のスペシャリストとして専門性を高めることも、複数の言語をカバーするゼネラリストとして活躍することも可能になっている状態です。
また、5年以上の実務経験を積むと、純粋な技術力だけでなく、プロジェクトマネジメントやステークホルダーとの調整力といったソフトスキルも身についているはずです。そのため、要件定義から設計・開発、保守・運用、そしてチームマネジメントといった、プロジェクト全体を管理・進行させる力が養われているでしょう。
このように、5年以上の実務経験があると、3年程度の実務経験者と比較すると総合的なスキルレベルや経験値が高くなるため、より複雑で規模の大きなプロジェクトや、責任のある立場での案件参画が可能になります。
エンジニアが独立するメリット
独立というと、収入が安定せずすべて自己責任になってしまうので、不安に思う方も多いと思います。しかし、エンジニアが独立するメリットはいくつもあります。
ここでは、エンジニアが独立するメリットについて、次の3つを解説します。
・年収アップが期待できる
・業務量を自分で調整できる
・働く場所や時間を選べる
年収アップが期待できる
エンジニアとして独立後に獲得する案件は、平均単価が高い案件が多く、企業に勤めていた時に比べて月給が上がる可能性が高いです。
Relanceの「フリーランスエンジニア白書」によると、独立後の平均年収は約576万円で、約55%の人が独立後に収入が上がったと回答しています。一方で、dodaの調査によると、企業に勤めているITエンジニアの平均年収は442万円となっています。
つまり、エンジニアとして独立することで、約130万円ほど年収が上がる可能性があります。
業務量を自分で調整できる
エンジニアが独立する大きなメリットは、自分のペースで自由に働ける点です。業務内容や業務量を自由に調整できるので、自分のペースで仕事を進めたり、自分にあったスキルの案件を選べます。また、業務量を自分で調整できるので、年収もある程度はコントロールできます。
気をつけておきたいのが、収入を増やすために案件を受注しすぎると、体調を崩したり、納期に間に合わなかったりするリスクがあることです。ある程度のゆとりを持って仕事を受注することで、クオリティの高い成果物を納品できます。
働く場所や時間を選べる
企業に勤めていると、毎日決まった時間に出社して、決まった労働時間だけ勤務をする必要があります。しかし、エンジニアとして独立すると、出社することがなくなり、パソコンさえあれば働く場所や時間は自由になります。
週3日だけ働くことや毎日午前中だけの勤務など、独立することで柔軟に働くことが可能です。
エンジニアが独立するときの懸念点と対策
エンジニアが独立するメリットはいくつもありますが、懸念点も挙げられます。ここからは、エンジニアが独立するときの懸念点と対策について解説をしていきます。
収入が安定しない
エンジニアが独立するデメリットとして、収入が安定しない点が挙げられます。エンジニアとして独立することで、独立前よりも年収が上がる可能性が高いですが、企業に勤めていた時のように、毎月一定の収入があるわけではありません。
そのため、案件獲得がうまくおこなえなかった月には、収入が減ってしまう可能性もあるでしょう。収入が減ってしまわないように、ポートフォリオを充実させる、SNSを使って営業するなど、継続的に案件獲得をおこなうことが大切と言えます。
案件獲得には実績が必要
エンジニアが独立後に案件を獲得するには、これまでの実績が大切になります。特に競合の多いエンジニアでは、クライアント側としては、実績のあるエンジニアに案件を依頼する方が安心と言えます。
そのため、エンジニアとして独立した直後で実績がない状態であれば、案件を獲得するために、クラウドソーシングサイトなどで低単価から実績を積む必要があります。
Relanceでは、担当者から評価されやすいスキルシートの書き方やフォーマットを提供しております。
案件獲得に不安を抱えているフリーランスエンジニアの方はぜひご活用ください!
⇒【すぐに使える!】案件獲得につながるスキルシートをダウンロードする(無料)
フリーランスが増えている
フリーランスボードの調査によると2023年のフリーランスエージェント市場は前年比142.8%という大幅な成長を遂げ、市場規模は2,063億円に達しました。
こうした状況を受けてITフリーランス人口も着実に増加しており、フリーランスエージェントに所属するITフリーランス人口は、2023年には約33万人に達し、前年から約5万人増加しました。この増加傾向は今後も続き、2027年には40万人を超え、国内IT人材の約3分の1をITフリーランス人材が占めると予測されています。
企業がITフリーランスを積極的に活用する背景には、DX推進やクラウド技術の普及、AI技術の発展などを受けて、それらを担える即戦力人材へのニーズが急増していることが挙げられます。
また、ITフリーランスになる人の数が急速に増えている要因としては、働き方改革の進展やリモートワークの普及が挙げられます。さらに、フリーランス新法の成立により法的な保護が整備され、安心して働ける環境が整いつつあることも、フリーランスへの新規参入を後押ししているでしょう。
ただし、フリーランス人材の増加に伴い、案件獲得の競争も激化しています。こうした環境下で案件を獲得するためには、先述した通り、技術力の向上やポートフォリオの充実、さらには新たなスキルの習得が重要となります。複数のプログラミング言語やフレームワークを習得していくなど、自身のスキルセットを開拓し、他のエンジニアとの差別化を図っていきましょう。
参考:フリーランスエージェント及びITフリーランス人材の市場調査(2024年版)|フリーランスボード
エンジニアとして独立を決めたらすべき4つの準備
エンジニアとしての独立を決めたら、以下の4点を行いましょう。
- ポートフォリオやスキルシートの作成
- 開業届と確定申告の準備
- クレジットカードや賃貸契約などの審査を通す
- フリーランスエージェントに登録
これらの準備をしっかりと行うことで、スムーズな独立開業が可能となります。以下では、それぞれの準備について解説していきます。
1.ポートフォリオやスキルシートの作成
エンジニアとして独立する際には、案件を獲得していけるよう実績やスキルをしっかりとアピールすることが重要です。
そのため、ポートフォリオを作成しましょう。ポートフォリオには、参画したプロジェクトの具体的な内容と自身の役割を明記します。たとえば、「大手ECサイトのショッピングカート機能の改修で、設計から実装までを担当し、Reactを用いてユーザビリティを向上させた」といった具体的な実績を記載します。
また、技術職向けの経歴書ともいわれる「スキルシート」の作成も重要です。スキルシートには、保有するIT関連資格を正式名称で記載し、得意分野や技術、過去に経験した業務内容を具体的に示します。加えて、プロジェクト実績として期間や役割、開発環境なども詳しく記述することもポイントです。
たとえば、Webアプリケーション開発者の場合、「フロントエンド開発5年の実務経験。React.jsを用いたSPAの設計・実装を得意とし、TypeScriptでの開発経験も豊富。直近2年間はスクラムマスターとして10名規模のチームマネジメントも担当」といった具合に、具体的なスキルと実績を簡潔に示しましょう。
ポートフォリオとスキルシートで、しっかりとスキルや実績をアピールすることで、独立後の案件獲得がスムーズになります。
2.開業届と確定申告の準備
エンジニアが独立して個人事業主となるには、開業届の提出が必要です。開業届は独立後1か月以内に提出しなければなりませんが、提出時期に注意が必要です。失業保険の給付を受ける予定がある場合は、開業届を提出すると失業保険の受給資格を失ってしまいます。そのため、給付金の受給を考慮して提出時期を調整することが賢明です。
また、独立を決めたら青色申告に関する手続きもするようにしましょう。会社員時代は白色申告ですが、独立後にはこの青色申告を選択することが可能です。青色申告とは、日々の取引を記帳し、より正確な収支管理を行う申告方式で、最大65万円の所得控除を受けられるなど白色申告と比べて多くのメリットがあります。
青色申告を希望する場合は、事前に青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。この申請書は原則として開業から2か月以内、もしくは青色申告書によって申告をしようとする年の3月15日までに提出する必要があります。
また、確定申告期間である2月から3月は税務署が非常に混雑します。この時期の開業手続きは長時間の待ち時間を強いられる可能性が高いです。そのため、比較的空いている時期に手続きを済ませることをおすすめします。
参考サイト:個人事業の開業届・廃業届出等手続|国税庁
参考サイト:所得税の青色申告承認申請手続|国税庁
3.クレジットカードや賃貸契約などの審査を通す
フリーランスエンジニアとして独立すると、社会的な信用力が低下することは避けられません。そのため、クレジットカードの発行や賃貸契約、各種ローンなど、審査が必要となる手続きは会社員のうちに済ませておくことが賢明です。
とくにクレジットカードについては、会社員時代の安定した収入や勤続年数が審査にプラスに働きます。フリーランスになってからの申請では、収入の不安定さを理由に審査が通りづらくなることが一般的です。そのため、クレジットカードは会社員として在籍している間に作成しておきましょう。
賃貸契約についても同様です。フリーランスは収入が不安定になりがちで、家賃補助などの福利厚生もないため、大家からは家賃滞納のリスクが高いと判断されることがあります。また、会社という組織に属していないことで、社会的信用度が相対的に低く見られる傾向にあります。そのため、引っ越しの予定がある場合は、できるだけ会社員のうちに新しい賃貸契約を結んでおくことが望ましいです。
4.フリーランスエージェントに登録
既存文を活用
退職後には健康保険や国民年金の切り替えを忘れずに!
会社を退職してフリーランスエンジニアとして独立する際、最も重要な手続きの一つが社会保障制度の切り替えです。とくに注意が必要なのは、法律上、退職後14日以内に健康保険と国民年金の切り替え手続きを行う必要があることです。14日という期限を過ぎても手続き自体は可能ですが、その間に医療費が発生した場合は全額自己負担となる可能性があります。
会社員時代は会社の健康保険組合に加入していましたが、退職後は国民健康保険への切り替えが必要です。ただし、一定の条件を満たす場合、任意継続被保険者として、一定の期間、元の健康保険に継続加入することも可能です。この選択肢は、とくに収入が安定しない独立直後の時期に検討する価値があるでしょう。
国民年金についても、厚生年金から切り替える手続きが必要です。この手続きを怠ると、後日未納分の納付書が送られてくることになります。さらに、延滞金が発生する可能性もあるため注意が必要です。なお、独立直後で保険料の支払いが困難な場合は、免除制度を利用できる場合もあります。
これらの手続きには退職日を証明する書類が必要となるため、会社を退職する際には、必要書類を確実に受け取っておくようにしましょう。
参考:退職後の健康保険について | 全国健康保険協会
参考:国民健康保険の加入・脱退の届出など|豊橋市役所
まとめ
エンジニアとして独立するためには、タイミングの見極めが重要です。十分なスキル・経験を持ち、継続的な案件獲得の見通しが立ったとき、資金的な余裕が整ったときが独立の好機となります。
独立のメリットとして、年収が高まることや働く場所や時間の自由度が高まることが挙げられます。一方で、収入の不安定さやフリーランスの増加による競争激化といった課題もあります。
これらの課題に対応するため、独立前にはしっかりとエンジニアとしてのスキル習得・実績積みに励むなどの準備をしていきましょう。
会社員として3〜5年以上の実務経験を積んだタイミングで、手厚く支援してくれるフリーランスエージェントなどを活用しつつ、ぜひ独立を検討してみてください。
無料で高単価案件を紹介してもらう
関連記事