フリーランスの手取りはいくら?計算方法や早見表についても紹介
「自分が支払うべき税金や保険料の金額について知りたい!」
「フリーランスになって収入は上がったけど、実際の手取り額は増えているの?」
フリーランスとして働き始め、お金の面でこのような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
フリーランスは、報酬をそのまま収入として受け取った後、確定申告を経て、まとめて税金を支払います。そのため、給与から税金などが天引きされる会社員と違い、毎月の手取り額を把握しにくいものです。
またフリーランスの場合は、会社員とは税金や保険料、年金の算出式が異なるため、同じ年収であれば会社員より手取りが減ってしまうことも少なくありません。
そこで本記事では、フリーランスが支払うべき税金や保険料、年金についてご紹介し、フリーランスと会社員の年収別手取り早見表、人物像別にフリーランスの手取り額シミュレーションを解説します。さらに、手取り額を最大化するための節税法と、節税後の手取り額シミュレーションについても解説しました。
本記事を参考に、収入に対して自分が得られる手取り額の目安について知り、できるだけ手取り額を増やせるように節税していきましょう。
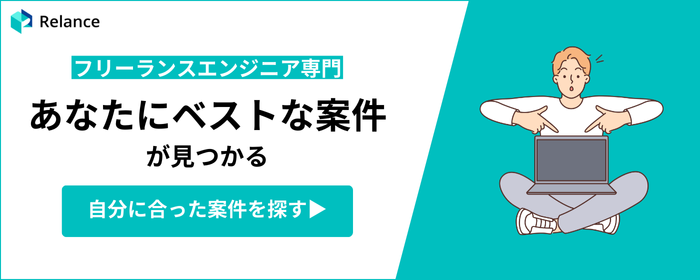
目次
同じ年収ならフリーランスは会社員より手取りは少ない
フリーランスと会社員の年収が同じであった場合、手取り額は一般的にフリーランスのほうが少なくなります。
手取りが少なくなる理由を理解するために、まずはフリーランスの手取りの仕組みについて知っておきましょう。
フリーランスの手取り額は以下の計算式で求められます。
手取り = 収入 -(必要経費 + 税金 + 国民健康保険料 + 国民年金)
フリーランスの手取りが少なくなる理由
手取りを算出するための計算式を見ると、フリーランスと会社員との違いとして、必要経費の有無と、保険が国民健康保険であるか社会保険であるかの2点に気付くでしょう。
ほかにも、フリーランスと会社員とでは税金の計算法についても違いが見られます。年金については、厚生年金を負担しなくてよい分、フリーランスのほうが安くなります。ただし、将来得られる年金額も少なくなってしまうことに、注意が必要です。
さきほどのフリーランスと会社員の違いを踏まえ、経費と税金、保険料それぞれの要素を深堀り、フリーランスのほうが会社員より手取りが少なくなる理由を解き明かしていきましょう。
フリーランスが同じ年収の会社員より手取りが少なくなる理由は、次の4つです。
・収入から必要経費が差し引かれる
・税金の計算方法が異なる
・税金の種類が増える
・保険料が高くなる
詳しく解説していきます。
収入から必要経費が差し引かれる
フリーランスが収入を得るためには、さまざまな費用がかかります。エンジニアであれば、PC、PC関連機器、机や椅子、専用ツール、仕事場所、通信環境、学習本などが必要となるでしょう。
フリーランスの手取りは、収入からこれらの費用が必要経費として差し引かれます。そのため、フリーランスは会社員より実質的な報酬が減ってしまうのです。
フリーランスの所得は、事業所得に分類されます。企業において、売上高から売上を上げるために要した費用を差し引いた額が利益になることと関連づければ、イメージがしやすいでしょう。
なお、(経費 ÷ 収入)× 100 で計算した値を経費率(%)と呼びます。一般的に、経費率が低いほど利益率が上がることになり、手取り額は増えるでしょう。
税金の計算方法が異なる
フリーランスと会社員とでは、税金の計算方法が異なります。
具体的にどのような違いがあるのか、確認しておきましょう。
所得税
会社員の場合、課税所得は給与から給与所得控除と所得控除を差し引いた額で計算されます。給与所得控除は給与の金額に対してそれぞれ定められているため、給与額を変化させない限り、会社員が自分で控除額を調整することはできません。
一方でフリーランスの場合は、収入から必要経費と所得控除を差し引いた課税所得を計算し、その金額に応じて所得税が課されます。
フリーランスは、確定申告にて自分で必要経費を申告します。経費計上できる額が少ない場合は課税所得が多くなり、結果として所得税も増えてしまうのです。
参考サイト::給与所得控除 | 国税庁
参考サイト:やさしい必要経費の知識|国税庁
住民税
住民税とは地方税を指し、居住する地域によって多少金額が異なります。所得割と均等割の2つに分かれているのが基本です。
「所得割」は、名前のとおり所得に応じて金額が決まります。先ほどの所得税と同様、収入から経費や所得控除を差し引いた課税所得に、地方自治体が定めた所得割税率を掛けることで計算します。
所得割税率は全国どの場所でも原則として10%であり、その内訳は一般的に道府県民税が4%、市町村民税が6%です。
「均等割」は、所得に関係なく定額が課せられます。均等割は各地方自治体によって異なり、東京都の場合は、都民税が1,500円、区市町村税が3,500円です。
住民税も課税所得によって金額が変わるため、フリーランスの経費の額によっては、会社員よりも税額が大きくなってしまう場合があります。
参考サイト:個人住民税|総務省
参考サイト:個人住民税 | 税金の種類 | 東京都主税局
税金の種類が増える
フリーランスになると、業種や収入によっては、会社員よりも支払わなければならない税金の種類が増える場合があります。
該当する税金を確認しておきましょう。
個人事業税
業種ごとに「個人事業税」が課せられます。個人事業税とは地方税の一種です。業種によって税率が異なります。
なお、エンジニアなど個人事業税の対象にならない業種もあるため、自身の従事する業務がどの業種にあたるのか、確認しておきましょう。
個人事業税の計算式は以下のとおりです。
{( 事業所得 - 必要経費 )- 事業主控除(290万円) }× 税率
営業期間が1年に満たない場合は月割額で計算され、その分の控除額も減ります。
消費税
フリーランスは、以下の条件を満たしている場合、消費税が発生します。
- 課税期間より前々年の課税売上高が1000万円を超える
- 前年の1月1日~6月30日の課税売上高または給与支払額が1000万円を超える
- 消費税課税事業者選択届出書を提出している
飲食業、宿泊業、一部の医療サービス、不動産賃貸業など特定の業種や活動は、売上金額にかかわらず消費税が課されます。
消費税は課税される前々年の売上をもとに決定するため、2年前の売上が1000万円を超えていれば、現在売上が全くない状態でも納税しなければなりません。
フリーランスが収める消費税の計算方法は、簡易課税方式を用いることが多いです。
消費税 = 課税売上高 × 消費税率 - 課税売上高 × 消費税率 × みなし仕入率
しかしながら2023年の10月からインボイス制度が始まります。免税事業者のままでいると仕入れ額税控除ができなくなり、取引してくれるクライアントが減り仕事も減ってしまう可能性があります。
フリーランスとして今までと変わらずに仕事を進めていくには課税事業者になることが必要となり、年間の売上高にかかわらず消費税を納める義務が発生することになるでしょう。
参考サイト:消費税のしくみ|国税庁
参考サイト:インボイス制度の概要|国税庁
保険料が高くなる
会社員の場合は会社と折半して社会保険料の半額を支払いますが、フリーランスは全額負担しなければなりません。
そのため、保険料の負担が増えてしまうのです。
国民健康保険の保険料は、市町村により異なります。さらに40歳以上になると追加されるのが、介護保険料です。
保険料にも住民税と同様に、所得割と均等割があります。
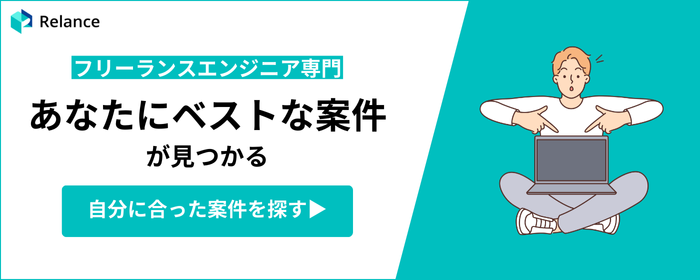
【年収別】フリーランスと会社員の手取り比較表
では、フリーランスと会社員では具体的にどのくらい手取りの差が生まれるのでしょうか。
エンジニア・東京都世田谷区在住・40歳未満の場合における、フリーランスと会社員の年収ごとの手取り額を見ていきましょう。
| 年収 | 所得税 | 住民税 | 国民健康保険 | 国民年金 | 手取り(フリーランス) | 手取り(会社員) |
| 300万円 | 5万円 | 10万円 | 19万円 | 20万円 | 187万円 | 238万円 |
| 400万円 | 8万円 | 17万円 | 26万円 | 20万円 | 249万円 | 314万円 |
| 500万円 | 14万円 | 24万円 | 34万円 | 20万円 | 308万円 | 388万円 |
| 600万円 | 21万円 | 32万円 | 42万円 | 20万円 | 366万円 | 460万円 |
| 700万円 | 34万円 | 39万円 | 49万円 | 20万円 | 419万円 | 527万円 |
| 800万円 | 48万円 | 46万円 | 57万円 | 20万円 | 469万円 | 591万円 |
| 900万円 | 63万円 | 53万円 | 65万円 | 20万円 | 519万円 | 660万円 |
| 1000万円 | 78万円 | 60万円 | 72万円 | 20万円 | 570万円 | 728万円 |
※所得控除は基礎控除と社会保険料控除のみを利用・1万円未満は四捨五入
フリーランスの条件:経費率20%・青色申告・個人事業税なし
比較してみると、実際に同じ年収でも、フリーランスの方が会社員より手取りが少なくなっていることが分かります。
フリーランスになって年収が増えたからといって、必ずしも手取り額が増えるわけではないことに注意が必要です。
【人物像別】フリーランスの税金・手取りシミュレーション
収入や職種、年齢、居住地によって、税額や手取り額はどのように変わってくるのでしょうか。
具体的な人物像を挙げて、税金額・手取り額をシミュレーションしていきましょう。ご自身に近い人物に当てはめて考えてみてください。
なお、青色申告をおこなっており、経費率は先ほどと同様20%である場合を想定しています。
人物像は以下のとおりです。
・月収60万円・エンジニア・35歳・品川区在住
・月収100万円・弁護士・40歳・大阪市在住
・月収40万円・デザイナー・30歳・横浜市在住
月収60万円・エンジニア・35歳・品川区在住
月収60万円・エンジニア・35歳・品川区在住の場合、手取り額は以下のとおりです。
| 所得税 | 住民税 | 国民健康保険 | 国民年金 | 手取り | |
| 月収60万円 | 3.0万円 | 3.4万円 | 4.2万円 | 1.7万円 | 35.7万円 |
| 年収720万円 | 36万円 | 40万円 | 51万円 | 20万円 | 429万円 |
この場合エンジニアであるため、個人事業税はかかりません。
月収100万円・弁護士・40歳・大阪市在住
月収100万円・弁護士・40歳・大阪市在住の場合、手取り額は以下のとおりです。
| 所得税 | 住民税 | 消費税 | 個人事業税 | 国民健康保険 | 国民年金 | 手取り | |
| 月収100万円 | 8.8万円 | 6.1万円 | 5.0万円 | 2.8万円 | 8.5万円 | 1.7万円 | 47.1万円 |
| 年収1200万円 | 105万円 | 74万円 | 60万円 | 34万円 | 102万円 | 20万円 | 566万円 |
弁護士であるため、5%の個人事業税がかかります。また、年収1000万を上回っているので、消費税の課税対象です。
月収40万円・デザイナー・30歳・横浜市在住
月収40万円・デザイナー・30歳・横浜市在住の場合の手取り額は以下の通りです。
| 所得税 | 住民税 | 個人事業税 | 国民健康保険 | 国民年金 | 手取り | |
| 月収40万円 | 1.0万円 | 1.9万円 | 0.4万円 | 2.8万円 | 1.7万円 | 24.2万円 |
| 年収480万 | 12万円 | 23万円 | 5万円 | 33万円 | 20万円 | 291万円 |
デザイナーであるため、5%の個人事業税がかかります。
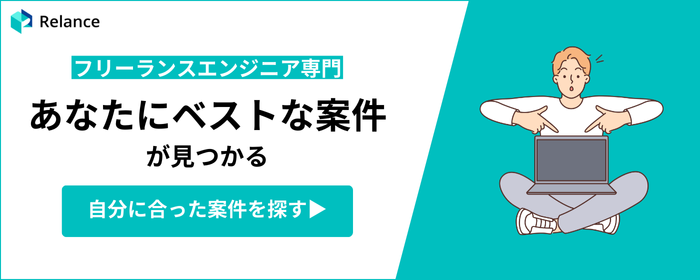
フリーランスが手取りを増やすための節税術
上記の表を見て、「税金や保険料が高い!」と感じた方は多いのではないでしょうか。
フリーランスは確かに税金など支払うものが大きいですが、節税策を講じることで手取り額を増やすこともできます。
賢く節税をして、手取り額を増やしていきましょう。
具体的な節税法は、以下の通りです。
・青色申告をする
・支出をできるだけ経費にする
・所得控除を利用する
・税理士に相談する
1つずつ解説していきます。
青色申告をする
フリーランスが確定申告をおこなう際、白色申告と青色申告の2種類の方法があります。白色申告では控除額が10万円ですが、青色申告をすることで最大65万円の控除が受けられます。
青色申告には正式な申告方法として、貸借対照表や損益計算書など複式簿記での記帳が必要です。その分、特別控除としてのメリットが受けられる仕組みになっています。
たとえば年収800万円、経費率20%のフリーランスの場合、支払い額、手取り額の申告方式による違いは、以下のとおりです。
| 所得税 | 住民税 | 国民健康保険 | 手取り | |
| 青色申告 | 48万円 | 46万円 | 57万円 | 469万円 |
| 白色申告 | 58万円 | 51万円 | 62万円 | 448万円 |
この場合、青色申告だと手取り額は469万円、白色申告だと448万円となり、21万円もの節税ができます。
青色申告で確定申告をおこなうには、その年の3月15日までに「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。開業をしたらすぐに提出するようにしましょう。
また、青色申告で確定申告をおこなう際には、会計ソフトの利用が便利です。会計や税務の知識がない方でも、簡単かつ正確に申告ができるようになるので、積極的に活用していくことをおすすめします。
参考サイト:青色申告制度 | 国税庁
支出をできるだけ経費にする
フリーランスの課税所得は、収入から必要経費や控除を引いた額で計算されます。したがって、事業に関係する支出をできるだけ経費に計上することで、節税対策となります。
必要経費に上限はありませんが、収入に関係のない私的な支出を経費計上してはいけません。過剰な経費計上は税務調査の対象にもなり得ますので、注意しましょう。
また、自宅で仕事をしている方の場合は、家賃や光熱費の一部を経費にできます。
フリーランスが経費計上できる勘定科目の具体例を挙げましたので、参考にしてください。
| 勘定科目 | 内容 |
| 旅費・交通費 | 出張や移動に伴う交通費、ガソリン代、駐車料金 |
| 通信費 | 電話料金、インターネット接続費、郵送料 |
| 接待交際費 | 業務に関係する飲食や接待の費用 |
| 広告宣伝費 | 広告や宣伝に関する費用、ウェブサイト制作費、広告料 |
| 会議費 | 会議に伴う会議場所のレンタル費、軽食、飲料 |
| 消耗品費 | パソコンや机、文房具などの消耗品費 |
| 雑費 | どの科目にも属さない、金額や内容が決まっていない経費 |
参考サイト:やさしい必要経費の知識 | 国税庁
所得控除を利用する
所得控除を利用することで、課税対象額を減らし、納税額も減らせます。
具体的な所得控除には以下のようなものがあります。
- 社会保険料控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 生命保険料控除
- 寄付金控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 医療費控除
国民健康保険料や国民年金も実は、社会保険料控除の対象となります。自身で生命保険や地震保険に加入している場合も、控除の対象です。また、配偶者や扶養家族がいる場合は、配偶者控除や扶養控除を受けられる場合があります。
自分が該当する所得控除を把握し、できるだけ課税所得を減らすようにしましょう。
参考サイト:所得控除のあらまし | 国税庁
税理士に相談する
税理士に相談すれば、正しく賢く節税できます。
税理士に依頼することで、経費にできるものが増えたり、利用できる控除を最大限活用することができたりなど、自分1人でおこなう場合より節税が実現できるでしょう。
また税理士は、申告書の作成や提出においても正確性を保証してくれます。確定申告では、ミスがあると追徴課税などのペナルティが課せられてしまうリスクがあるため、正しく手続きをすることが重要です。
その点において税理士は、税務署の規定や書類の整備に詳しく、ミスや不備が生じる可能性を軽減してくれます。
税務や会計は内容が煩雑で、自分では理解が難しく、時間を要するものです。手続きや書類の作成、期限の管理などを税理士に任せることで、フリーランス自身の負担を軽減し、業務に集中できる時間を確保できるというメリットがあります。
フリーランスエンジニアと正社員エンジニアのお金についてもっと知りたいなら!
節税した場合の税金・手取りシミュレーション
これまでに説明した節税対策をおこなった場合、手取り額はどのように変化するのでしょうか。
本シミュレーションでは、経費率を20%、30%、40%にしたときの税金と国民健康保険料の金額について先ほどの人物像ごとに比較しました。
すべての場合において、経費率が高まるほど支払うべき金額が減り、節税できていることがわかります。
月収60万円・エンジニア・35歳・品川区在住
月収60万円・エンジニア・35歳・品川区在住の場合の経費率ごとの税金と国民健康保険料の金額は以下の通りです。
月間
| 所得税 | 住民税 | 国民健康保険 | 計 | |
| 経費率20% | 3.0万円 | 3.4万円 | 4.2万円 | 10.6万円 |
| 経費率30% | 2.0万円 | 2.8万円 | 3.7万円 | 8.4万円 |
| 経費率40% | 1.4万円 | 2.3万円 | 3.1万円 | 6.8万円 |
年間
| 所得税 | 住民税 | 国民健康保険 | 計 | |
| 経費率20% | 36万円 | 40万円 | 51万円 | 128万円 |
| 経費率30% | 23万円 | 34万円 | 44万円 | 101万円 |
| 経費率40% | 17万円 | 27万円 | 37万円 | 81万円 |
月収100万円・弁護士・40歳・大阪市在住
月収100万円・弁護士・40歳・大阪市在住の場合の経費率ごとの税金と国民健康保険料の金額は以下の通りです。
月間
| 所得税 | 住民税 | 消費税 | 個人事業税 | 国民健康保険 | 計 | |
| 経費率20% | 8.8万円 | 6.1万円 | 5.0万円 | 2.8万円 | 8.5万円 | 31.2万円 |
| 経費率30% | 6.7万円 | 5.1万円 | 5.0万円 | 2.3万円 | 8.5万円 | 27.6万円 |
| 経費率40% | 4.7万円 | 4.2万円 | 5.0万円 | 1.8万円 | 8.1万円 | 23.7万円 |
年間
| 所得税 | 住民税 | 消費税 | 個人事業税 | 国民健康保険 | 計 | |
| 経費率30% | 105万円 | 74万円 | 60万円 | 34万円 | 102万円 | 374万円 |
| 経費率30% | 80万円 | 62万円 | 60万円 | 28万円 | 102万円 | 331万円 |
| 経費率40% | 56万円 | 50万円 | 60万円 | 22万円 | 97万円 | 285万円 |
月収40万円・デザイナー・30歳・横浜市在住
月収40万円・デザイナー・30歳・横浜市在住の場合の経費率ごとの税金と国民健康保険料の金額は以下の通りです。
月間
| 所得税 | 住民税 | 個人事業税 | 国民健康保険 | 計 | |
| 経費率20% | 1.0万円 | 1.9万円 | 0.4万円 | 2.8万円 | 6.1万円 |
| 経費率30% | 0.7万円 | 1.6万円 | 0.2万円 | 2.4万円 | 4.8万円 |
| 経費率40% | 0.6万円 | 1.2万円 | 0万円 | 1.9万円 | 3.7万円 |
年間
| 所得税 | 住民税 | 個人事業税 | 国民健康保険 | 計 | |
| 経費率20% | 12万円 | 23万円 | 5万円 | 33万円 | 73万円 |
| 経費率30% | 9万円 | 19万円 | 2万円 | 28万円 | 58万円 |
| 経費率40% | 7万円 | 14万円 | 0万円 | 23万円 | 44万円 |
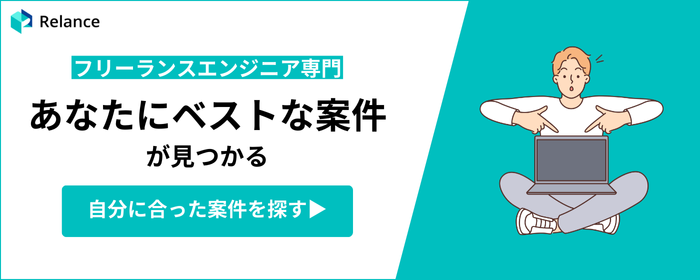
まとめ
本記事では、フリーランスが支払うべき税金や保険料、そして手取り額について解説しました。
フリーランスは、同じ年収の会社員と比較して手取りが少なくなります。これは、経費計上などが関係し、また税金や保険料についても会社員とは計算方法などが異なるためです。
手取りを最大化するためには、青色申告や経費、所得控除を上手く利用して節税対策を講じることが重要といえます。
本記事を参考に、手取り額を見積もり、自身ができる節税対策に取り組みましょう。
関連記事


